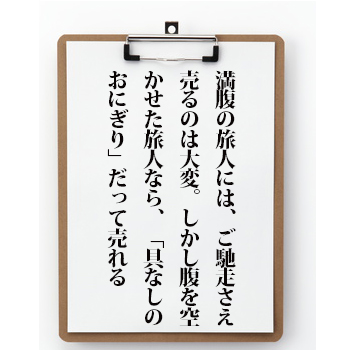
「ウチは、全然マーケティングができていないですね」
先日、コンサルティング中に「その商品のシェアはどの程度ですか? 推定でも良いので教えてください」とお尋ねしたところ、「いやー、調べたこともないですねー」と返答が返ってきました。
非常に“売れる匂い”のする商品だったので、どの程度の「売上拡大余地」があるのかを知りたかったのですが、想定される市場規模も競合他社の動向も把握していない状態では、どれほどの成長ポテンシャルがあるのかを判断する術がありません。
言い換えれば、「どこまで売れるのか」「どれほどの資源を投入すべきか」の意思決定ができないのです。
そうお伝えすると、冒頭のような返答が返ってきたのです。
これからの時代、「なんとなく売れている」では通用しません。
市場はますます細分化し、競合はスピードと精度を武器にシェアを奪いにきます。
感覚的な経営や、過去の成功体験だけでは、新しい顧客の獲得も、既存顧客の維持すら難しくなってきているのです。
では、マーケティングができていない状態から、どうすれば抜け出せるのか?
それは、「知らないことを知る」ことから始まります。
つまり、問いを立て、調べ、仮説を持つことです。
売れる匂いのする商品―。
これはすでに一定数売れている商品だったのですが、そもそも「なぜ売れているのか?」という問いを立てることから始めなければなりません。
と言うと、多くの企業にこの質問をすると、十中八九「商品の機能」を説明し始めます。
いえいえ、知りたいのは機能ではありません。
それはホームページを見ればわかります。
マーケティングの問いとは、その機能を使って、お客さんはどのようなベネフィットを享受しているのか?
もっと具体的にいえば、どんなメリットを感じていて、どの程度の経済効果をお客様は感じているのか?という「顧客目線での体験価値」なのです。
もちろん、トップセールスマンは、受注数に比例して、この顧客の購入理由を知っていることもあります。
しかしながら、購入後に実感した「メリット」や「経済効果」まで把握しているケースは、驚くほどありません。
トップセールスマンですら、「顧客目線での体験価値」を言語化できないのですから、他の営業パーソンが掌握しているはずもありません。
これは、「組織的営業力」が、活かしきれていないと断言できる状態にあります。
「それでも売れているから良いじゃないですか!」と反論する方もいます。
厳しいことを言いますが、それは営業が優秀だからではありません。
お客様が優秀なのです。
「機能説明」を聞いたときに、「このようなベネフィットや経済効果が得られる!」と変換してくれて、それを上長にわかりやすく理解できるよう、稟議書を書いてくれているから、受注に結びついているのです。
本来であれば、売り手である営業サイドが、その「変換作業」までやってあげなければなりません。
つまり、「この機能を使うと業務がこう変わる」「その結果、◯万円のコスト削減になる」…など、一連の価値のストーリーを、先回りして提示するのが営業の本質的な役割です。
これは、営業だけの役割ではありません。
本来であれば、商品企画の段階から、この一連の価値ストーリーが考慮されていなければ、どの程度の売上が上がるかを想定することすらできないはずなのです。
大事なことなので、もう一度言います。
製品が持つ「機能」を顧客価値に変換し、経済効果まで推定することが、商品企画の肝であり、かつ営業が顧客に伝えなければならない中心的なメッセージなのです。
これができていなければ、どれだけ素晴らしい技術であっても、「売れる理由」が社内でも社外でも共有されず、結果として価格勝負に巻き込まれるか、ただのスペックの羅列で終わってしまいます。
よく「うちの商品は他社よりも高機能です」と自信満々に語る方がいます。
しかし、高機能=高価値ではありません。
顧客が求めているのは「機能」ではなく「結果」です。
その機能を使って、どのような結果が手に入るのか―このゴールを描ききれなければ、売上は思うように伸びないのです。
マーケティングの本質は、“顧客価値の創造”です。
顧客以上に顧客を知り、価値を創造できてこそ、マーケティングは機能し始めます。
対象となる顧客層は、どの程度の厚みがあるのか――これが市場です。
顧客が商品を使うメリットを把握し、その顧客層の厚み……つまり市場が確定できれば、「どれだけ売れそうなのか」の解像度が上がります。
苦戦を強いられそうな1億円市場と、競合が不在で顧客の痛みが激しい10億円市場とでは、経営資源の投入量も大きく変わります。
満腹の旅人には、ご馳走さえ売るのは大変ですが、腹を空かせた旅人なら、「具なしのおにぎり」だって売れるわけです。
だったら、腹を空かせた旅人が多く集まる「場所」を探し当て、そこで大量の売り子を派遣した方が、ビジネスが上昇気流に乗るのは、火を見るよりも明らかなハズです。
このアタリマエの論理を、どこまで組織的に徹底できるか?
これが、マーケティング思考の企業と言えます。
整理すると、「顧客価値の創造」から「市場の確定(顧客層の厚み)」がわかったら、彼らがどれだけ腹を空かせているか――つまり、競合や代替品では満たされていない「不満」や「未解決の課題」を浮き彫りにするのです。
そうすれば、どの程度「そのビジネス」に力を入れるべきかが、手に取るようにわかります。
これが、マーケティングの第一機能です。
第二機能は、第一機能で明らかになった価値を、そのまま市場に的確に伝達し、浸透させることです。
平たく言うと、WebやSNS、広告、DM、営業活動などは、この「価値の伝達と浸透」に尽力する第二機能にあたります。
売上責任は、この第一機能・第二機能の双方にありますが、出発点である第一機能がぼやけてしまっていては、当然ながら第二機能はうまく働きません。
この第一機能と第二機能が有機的につながった状態こそが、「戦略的マーケティング」が機能している状態です。
経営において最も重要なのは、「正しく、力を入れること」です。
マーケティングとは、経営資源を“正しい場所”に“正しい方法”で投下するための設計図です。
つまり、単なる販促活動ではなく、経営の羅針盤であるべきなのです。
第一機能で価値をつくり…
第二機能で価値を伝達し…
最終的に顧客との信頼関係を築いていく。
その連鎖によって、安定的で強い収益構造を育てることが“マーケティングの理想的姿”です。
御社は、マーケティングの理想的な姿を組織的に追求していますか?
