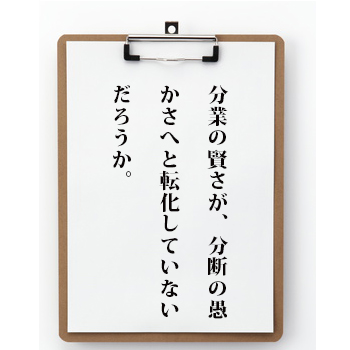
「そもそも、部門横断チームが業績を伸ばす理由とは何でしょうか?」
先週のコラムを読んだ読者の方から、そんな“そもそも論”のご質問をいただきました。
セミナーなどではよくお話ししているテーマですが、振り返ってみると、コラムで明示的に扱ったことはなかったようです。
そこで今回は、あらためて「部門横断チームが業績向上に寄与する理由」について、簡潔にお伝えしていきたいと思います。
「部門横断チーム」と対照的な概念として思い浮かぶのが、「分業制」です。
分業は、現代の組織構造においてスタンダードな考え方であり、それが成果を最大化するための合理的な仕組みであることは間違いありません。
営業は、商品やサービスを販売すると同時に、現場で得たリアルな声を社内にフィードバックする役割を担っています。
開発部門は、プロダクトアウトやマーケットインといった視点をもとに、製品やサービスの設計・改良を行います。
さらに製造部門は、それらを効率的かつ安定的に生産する責任を負い、品質やコストを管理します。
また、研究部門はさらにその先の未来を見据えて、既存技術のボトルネックを取り除くような新しい知見や技術の可能性を探る。
このように、それぞれの役割が明確に分かれていることで、専門性が磨かれ、効率的に成果を上げることができるているのは、間違いのない事実です。
人類の進化は、分業制とともに歩んできたのかもしれません。
古代の狩猟民族の姿に思いを馳せると、獲物を追う者、武器をつくる者、新たな狩猟道具を工夫する者など、それぞれが役割を担い、協力しながら集団で生き抜いていた光景が思い浮かびます。
・動体視力や運動能力に長けた者は狩りに出かける
・手先が器用な者は武器をつくる
・そして、知的好奇心の旺盛な者は、毒矢や罠など、より効率的な手法を編み出す
優秀なチームは、こうした分業の中で、それぞれが自らの得意分野で力を発揮し、集団として大きな成果を上げていくー。
その姿は「サピエンス全史」などの書籍を通じて人類の軌跡に触れる中で、あらためて気づかされることでもあります。
そう考えると「分業」は、合理的かつ本能的に備わった集団最適の知恵とも言えるかもしれません。
しかし一方で、現代の企業活動においては、この“分業の賢さ”が、時として“分断の愚かさ”へと転化してしまうリスクを孕んでいます。
つまり、「自分の仕事はここまで」「あとは他部署の仕事」といった意識が強くなりすぎると、組織全体の目的が見えづらくなり、各部門の最適化ばかりが優先されてしまいます。
・営業は、製品が売れない原因を「営業力不足」と一方的に押し付けられ、理不尽さに憤りを感じている
・開発は、「こんなに優れた商品をつくっているのに、なぜ売れないのか」と疑問を抱える
・研究は、誰も思いつかなかった革新的な素材を開発したものの、組織が製品化に関心を示さず、成果が宙に浮いたままになっている——。
こんな不満の声は、新橋の居酒屋にでも行けば、あちらこちらから聞こえてくるものです。
それぞれが高い専門性とプロ意識を持って仕事に取り組んでいても、「分断されたままの分業」では、成果にはつながりません。むしろ、部門間の摩擦を生み出す原因にもなりかねないのです。
売上のボトルネックが、「分断されたままの分業」によって生じているケースは、決して少ないことに経営層は気づく必要があります。
その理由は、先週号のコラム「共通言語が生みだす『部門横断チーム』の実践知」でお伝えした通り、部門の垣根を越えた「顧客視点での経営」が欠如してしまうからです。
経営の目的とは、自社の技術や商品を通じて、顧客や社会をより良く導くことにあります。
営業も、開発も、研究も、みなその一つの目的を実現するために本来は存在しているはずです。
しかし、いつしかその原点を見失い、自部門の目標や成果だけを追いかけるようになると、組織は“セクショナリズム”に陥っていきます。
このセクショナリズムこそが、顧客視点を失わせ、やがて売上目標の壁にぶつかり、減収や減益を招く最大の要因につながっていくのです。
反対に、顧客や社会に貢献する姿勢が伝わり、買い手がその価値を信頼してくれるようになれば、自然と購買活動は促進され、業績も伸びていきます。
わかりやすい例として、「リバースアンブレラ(逆さ傘)」のヒットがあります。
通常の傘は閉じると濡れた面が外側になり、満員電車の中や車内で他人や荷物を濡らしてしまうことがあります。
リバースアンブレラは、濡れた面が内側に閉じる構造を持ち、他人や自分の荷物を濡らさない。
車に乗る際も、スマートに傘を収納できるため、車内を濡らす心配もありません。
成熟市場である「傘」というプロダクトであっても、こうした見過ごされていた不便さ…つまり顧客の痛点は、まだまだ存在するのです。
・営業部門が、顧客や市場の不満や不快感にいち早く気づく
・技術部門が、その不満を新たな視点と技術力で、どう解決していくかを探る
こうした部門間の連携によって新たな価値が生み出し、結果としての売上を伸ばしていくことが、部門横断チームのあるべき姿です。
「私たちの技術は、誰にとって、どのような価値へと変換できるのか?」
「私たちの事業分野で、顧客が困っていること、あるいは満たされていない欲求は何か?」
こうした問いを、それぞれの部門が個別に考えるのではなく、営業・開発・製造・研究など、関係するすべての部門がチームとして一丸となって考えること…。それこそが、非常に重要なプロセスだと感じています。
部門横断チームとは、単なるプロジェクト体ではなく、「価値創造の土壌」を耕す仕組みそのものです。
御社の組織は、チーム一丸となって「顧客の価値」を追求する文化が醸成されていますか?
