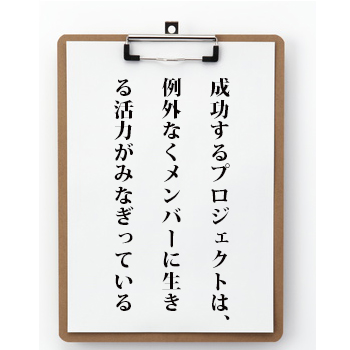
『失敗するプロジェクトと成功するプロジェクトの違いって何ですか?』
新規のコンサルティング契約時にご質問を頂いた社長さんの言葉です。
コンサルティングという仕事に携わる中、様々な業種、規模の営業体制の改革プロジェクトや新規事業の立ち上げ支援に伴走してきました。
15年間の活動の中で、成功するプロジェクトもあれば、大した成果をあげることの出来なかったプロジェクトもあります。
冒頭のご質問にお応えすると同時に、我々のような外部支援者が参画するしないに関わらず、成功するプロジェクトも失敗に終わるプロジェクトの共通点を経験談からお伝えしたいと思います。
成功するプロジェクトには、様々な要因が影響しあって成立するものですが、ここではスタートラインで絶対的に守らなければならないことをお示ししたいと思います。
ポイントを3つに絞ってお伝えします。
一つは、運営の体制
二つ目は、ゴール設定
三つ目は、リーダーのチャレンジ精神です。
一つ目の運営体制では、絶対的に注意しなければならないことを1つだけお伝えしたいと思います。
それは、裁量の余地を残して、プロジェクトを推進させるということです。
ざっくり言うとプロジェクトの目的と目標、それと禁止事項だけを伝えて、実行プログラムは部下に任せることが最大のポイントとなります。
もちろん、手掛かりがないと最初の一歩を踏み出すことができない場合が多いので、方向性や戦略のアウトラインだけを提示する方がスピード感はでるでしょう。
また「こんな感じかな」というざっくりな具体的行動案を示して、完成された行動計画じゃないからあとは自分達で考えてね!と、お手本を示す必要のある場合もあるでしょう。
しかしながら、「こうやるぞ!こうじゃいとダメだ!」的な運営をしていしまうと、チームメンバーの思考力を奪い、実行レベルでの試行錯誤が生まれず、事なかれ主義のまま失敗へと突き進むリスクが高まります。
実際、私が関与してきたプロジェクトでも「先生が答えを持っている」とおんぶに抱っこでくるケースは、あまりうまくいきませんでした。
逆に、我々が提示したやり方や考え方を受け取り、「こんな感じでやりたい」「こんな風に進めたい」と具体的行動については、自分たちで考え行動するケースや、我々が具体的なアイデアを出しても、それに創意工夫を加える組織は、振り返ってみると過去例外なく成功していました。
最終的な実行計画を自分たちで決定し、主体的に動く雰囲気をどうつくり出すか。
この「自ら考え、動くチーム」こそが、プロジェクト成功のカギを握っているのです。
もちろん、強烈な個性をもった創業社長がアイデアに行き詰まり、我々と共創することで、明確な方針を打ち出し、社長の強烈な推進力の元に成功したプロジェクトもあります。
しかし、その創業社長が引退した途端に社員はどこを向いて仕事をすれば良いのか右往左往しはじめ、業績低迷に陥ったケースも見てきました。
企業の社会的責任がゴーイングコンサーンであるならば、やはり「自ら考え、動くチーム」を育成すべきなのではないでしょうか。
他にも運営体制で抑えなえればならないポイントはありますが、割愛します。
成功するプロジェクトのあり方に焦点を合わせたいので、次のテーマに行きたいと思います。
二つ目は、いうまでもなく明確なゴール設定です。
以前、大手化粧品メーカーが、新規事業を企画しよう!と「部門横断チーム」を作って失敗したケースを直接担当者から聞いたことがあります。
敗因は、ゴール設定が曖昧だったことです。
新入社員から中堅社員まで幅広く集まったものの、活動の内容は「勉強会」の域を出ませんでした。直属の上司からは「そんな勉強会に時間を割くな。それよりも通常業務を優先しろ」と命じられる。
一方でプロジェクトの課題提出も求められ、メンバーたちはツーボスシステム(複数の上司から指示を受ける体制)の板挟みに苦しみました。結果として、わずか1年ほどで空中分解してしまったそうです。
もちろん、プロジェクトの立ち上げ時点ではゴールが多少曖昧でも構いません。
しかし、「新規事業を立ち上げよう!」という号令がかかった時点で、必ず以下のような問いを明確にしなければなりません。
・なぜ、今、新規事業が必要なのか
・成果(ゴール)をどう定義する
・なぜ、その成果を我々は追求するのか
こうした問いに明確に答え、プロジェクトの存在意義を誰に対しても説明できるレベルまで言語化し、メンバー全員が共有することが、成功への第一歩となります。
そして、最も重要なのは、最終ゴールに至るまでのプロセスに「小さな成功体験(中間目標)」を設けることです。
この小さな成功は、チーム内の士気を高めるだけでなく、プロジェクト外のメンバーからも協力を得やすくなるなど、社内に良い波及効果をもたらします。
実際、私が携わったプロジェクトで、既存商品の価格競争を打破するために新たな販路を模索した際、最初はわずか500通のダイレクトメールからスタートしました。そこで得た小さな成功体験がチームに自信を与え、その後は展示会出展や地道な営業活動を通じて、最終的には事業規模を7倍に拡大させることに成功しました。
別の新規事業プロジェクトでは、製品開発の前にコンセプトを明確化し、提案書ベースでテストセールスを実施。「売れる実感」をつかむと同時に、見込み客を獲得した上で商品化に進んだことで、販売開始直後から売上急拡大!という成果を上げたケースを幾度も経験してきています。
「小さなゴールをどこに設定し、それをどう達成するか」
この一点に、チーム全員が神経を集中させるような空気感をつくること。
それが、成功プロジェクトを推進するための土台となることを、15年におよぶ経験の中で学び、確信をもってお伝えしています。
最後の三つ目の要素は、経営者やプロジェクトリーダーの「チャレンジ精神」です。
私たちは参謀役としてプロジェクトに関与することが多いのですが、どれほど優れた体制や明確なゴールが整っていても、チャレンジ精神がなければプロジェクトの成功は望めません。
人間はどうしても、過去の経験から物事を発想しがちです。
しかし、新たな試みに挑むプロジェクトであれば、既存の延長線ではなく、道なき道を切り開く必要があります。
このときに重要になるのが、「アナロジー」と「勘(直感)」です。
アナロジーとは、「これは何かに似ていないか?」「何かと共通点はないか?」と問いかけることです。
つまり、異業種の事例を抽象化して自分たちのケースに応用する思考法です。
たとえば、製造業の自動化プロジェクトが、実は飲食業のオペレーション改善と構造的に似ていることがあります。また、まったく異なる業界の販売戦略が、自社の営業改革に役立つことも少なくありません。こうした“類推力”が、新たなアイデアの源泉となるのです。
そして、そのアイデアを実行に移すうえで求められるのが「勘(直感)」です。
ここで言う勘とは、単なる思いつきではなく、「勝ちパターン」に基づいたゴールへの道筋がぼんやりとでも見えた瞬間に働く感覚です。
プロジェクトの最中に、私がよく「それは金の匂いがしますね」と発言する時は、この「勘」が働くときです。
この時、成功するプロジェクトの場合は、社長や優秀なメンバーとチャンネルが合い、カチッとチャンネルがあう感覚を覚えます。
他の実務担当メンバーは、ポカンと口を開けることもありますが、それでも「戦略の意図や他業界の成功事例を示していくと、徐々に理解し始めてくれます。
そして、ある程度具体的なアイデアまで落とし込めると、「それなら、こうした方がもっと良いのでは?」と、活発に意見が出るようになるー。
そして最終的に、社長やリーダーが「よし、それで行こう!」とチャレンジングな意思決定を下したとき… そのプロジェクトは一念岩をも通す転換点となる経験もこれまで幾度となく体験してきました。
もうここまで来ると、早く行動したくてウズウズしてきます。
ビジネスほど、楽しい遊びはありません。
成功するプロジェクトは、例外なくメンバーに生きる活力がみなぎっています。
自ら成果を出そうと、自分の頭で考え、行動し、影響力を発揮しようとしています。
御社は、成功するプロジェクトの要所をいくつ抑えていましたか?
