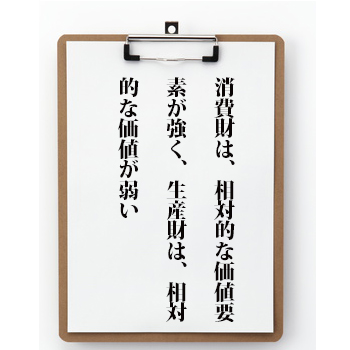
「ジャングリアのレポートは面白かったです。でもマーケティングの神様が何故あのような失態をするのでしょうか?マーケティングって、難しいですね」
先日、コラムを読んだクライアント企業の役員と一献傾けながらお話ししていた時の会話です。
マーケティングを一言でシンプルに表現すると、価値を作り、価値を伝達することです。
価値は、万人に通用するものはなく、ある特定の対象者(ターゲット)が感じるものです。
こうして、シンプルに考えると決して難しいものではありません。
しかしながら「価値」という概念自体が非常に厄介な存在です。
そのため、成果を上げることを目標に掲げた途端、マーケティングは一気に複雑になっていきます。
そもそも「価値」とは、顧客の状況や時代背景、競合の動向、さらには社会的なトレンドによって常に変化します。
自社で「これが価値だ」と定義したとしても、それが本当に市場や顧客に響くのかどうかは、実際に世に出してみるまで分からないことが多いのです。
つまり、「価値」という概念を広義に捉えると「絶対的な価値」ではなく、「相対的な価値」になるので、企業として“誰にとっての価値”なのかを明確に定義することが極めて難しくなるのです。
例えば、ジャングリアのコンセプトは、「Power Vacance!!(パワーバカンス)」です。
これは、沖縄の豊かな大自然を舞台に、本物の自然体験とエンターテイメントを融合させた、他では味わえない特別なバカンスを提供するというものです。
非日常の中で興奮と感動を味わってほしい、という「価値」を生み出したのですが、個人的には、この「価値」を感じることができませんでした。
理由は、世界自然遺産「やんばる」という手つかずの大自然や美しい「エメラルドグリーの海」がすぐ近くにあるのに、わざわざフィクションの世界観を味わう必要がないと感じた為です。
もちろん、家族連れなどのターゲットを想定した場合、ホンモノの自然は、不快な生物に遭遇したり、危険な環境に晒される可能性があり、心から楽しむにはハードルが高いと感じる人たちもいるでしょう。
そのため、「フェイクであっても、安全で快適に自然の魅力だけを凝縮して楽しめる」というジャングリアの価値を実感できる「顧客層」が存在するのも確かです。
ある人たちにとっては価値があるけど、ある人たちにとっては、無価値である…
これがまさに「価値の相対性」です。
ここで産業財マーケティングに視点を移してみましょう。
産業財(BtoB)と消費財(BtoC)は、求められるニーズが本質的に異なります。
実務家の視点で整理してみましょう。
消費財のニーズは感情的であり、かつ多様なニーズに対して「価値創造」の着眼点を置く必要があります。
人によって、「好み」「安心感」「楽しさ」など”相対的に異なる”感情的な価値が存在します。
また、「イメージ」「デザイン」など消費生活者の多様なニーズにも、着眼する必要性があります。
一方、生産財の場合は、経済合理性に基づく「論理的ニーズ」が中心です。
比較すると、消費財は、相対的な価値要素が強く、生産財は、絶対的な価値に帰着しやすいことが分かります。
購入目的の多くが「経済合理性」に基づくものが主となるからです。
藤冨がセミナーでよくお伝えしている「生産財のセールスポイントは、必ず”財務諸表”に影響している」という表現は、まさにここを説明しているのです。
経済合理性に基づくニーズに行き着くのですから、価値の創造は「売上上昇」「経費節減」「BSの改善(資産効率の向上、在庫削減、回転率改善)」など、企業経営に直結する指標を意識したものでなくてはなりません。
つまり、生産財マーケティングにおいては、顧客企業の経営者や意思決定者が抱える課題に対して、「具体的にどのような財務的インパクトをもたらすのか」を明確に示すことが効果的なのです。
しかしながら、多くの製造業企業では、自社製品の機能や性能をアピールすることに偏りがちです。
その結果、競合との比較がスペックや価格競争にとどまり、十分な収益を確保できない状況が発生しています。
なぜでしょうか。
それは、「価値の構造化」まで突き詰めていないケースが多いからです。
価値の構造化とは、自社製品やサービスが顧客企業の経営に与えるインパクトを具体的に整理し、財務的指標と連動させて提案内容を伝えることです。
例えば、生産ラインで使用する新しい設備を導入するケースを考えてみましょう。
設備を販売する側は、単に「性能が良い」「耐久性が高い」と説明するだけでは不十分です。
その設備が導入されることで、「生産効率が〇%向上し、生産コストが年間〇〇円削減できる」「メンテナンスコストが従来の設備と比べて〇〇円節減できる」といった、財務諸表に具体的に反映される効果を数値化して示す必要があります。
このように、顧客が直面している経営課題をしっかり捉え、自社製品の価値を財務的な視点から構造化し、具体的な数値で表現できれば、意思決定者は容易にその価値を理解し、購買行動へとつながるでしょう。
生産財マーケティングは、「財務諸表に直結した価値」を明確に打ち出すことによって、論理的な顧客ニーズに対する説得力を高めることができるのです。
いかがでしょうか。
消費財マーケティングは、相対的な価値に目を向けるため非常に複雑な価値創造プロセスが必要になります。
一方、生産財マーケティングは絶対的な価値創造に着眼するため、比較的シンプルな価値創造プロセスとなります。
もちろん「価値の構造化」の着眼点によって「成果」は雲泥の差となります。
では、成果を左右する「価値の構造化」を成功させるためには、どのようなポイントを押さえれば良いのでしょうか。
おおまかに分けて3つの視点があります。
1つ目は、「顧客の課題の本質を理解する」こと
2つ目は、「経営成果と連動した数値表現」をつき詰めること
3つ目は、「階層別のストーリー展開」をクリエイティブすること
この3つの視点です。
長文になってしまったので、内容については、次号(661話)で詳しくお伝え致します。
次号もどうぞご期待ください。
