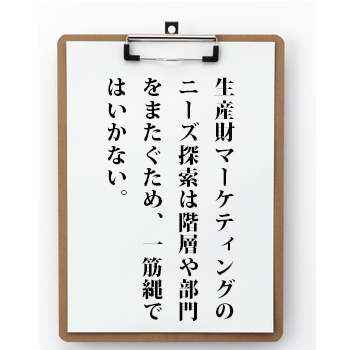
本号のコラムは、先週の「第660話 なぜ、生産財のマーケティングは消費財よりシンプルなのか」の続きをお届けします。
▼660話のポッドキャストをテスト的に公開しました。ぜひご視聴ください▼ https://youtu.be/0_yMZD0FKK0
前号では「価値の構造化」には3つの視点があると示し、「詳細は次号で」と締めくくりました。
今回は、その3つの視点について具体的に解説していきます。
「価値の構造化」とは、自社製品やサービスの価値を“顧客の経営成果”に結びつけ、数値や根拠とともに体系的に整理して伝えることです。
つまり、売り手が提供する製品を通じて、買い手の経営にどのような影響を与えたのか―
この問いに対し、明確かつ説得力ある答えを用意することだと言えます。
この「価値の構造化」を明確にできれば、製品は性能や価格だけでなく「経営改善の手段」として認識され、意思決定者の優先順位リストに上がってくるのです。
その「価値の構造化」を成功させるための3つの視点は、以下の通りです。
1つ目が、顧客の課題の本質を理解すること
2つ目が、経営成果と連動した数値表現を突き詰めること
3つ目が、階層別のストーリー展開を設計することです。
順を追って解説しましょう。
1つ目の「顧客の課題の本質を理解する」は、表層的な“要望”と、経営数値に影響する“真因”を切り分けることが出発点になります。
現場ヒアリングでは「困っていること」を並べるだけでなく、次の5つの視点でファクトとなる一次情報を集めることが重要です。
①発生頻度(どのくらいの頻度で起きるか)
②影響範囲(誰・どの工程に波及するか)
③金額換算(時間・人件費・材料ロスに換算するといくらか)
④再現性(同条件でいつでも発生するか)
⑤回避策の有無(既存手段でどこまで軽減できるか)
つまり、相手が潜在的・顕在的に感じている「痛点」の全体像を可視化するのです。
ここで有効なのが「作業指標 → 業務指標 → 財務指標」という三段ロジックです。
たとえば「段取り時間が長い(作業)」という要望があった場合、これを掘り下げると「日産能力の制約」や「残業時間の増加」といった業務課題につながっていることが分かります。
さらにその業務課題を深掘りすれば、「外注費や労務費の増加」「機会損失の発生」といった財務面の悪影響に行き着きます。
こうした構造的な関係性を明らかにすることが、生産財マーケティングの出発点となるのです。
2つ目の「経営成果と連動した数値表現を突き詰める」とは、我々の提案が相手企業にとって「どのような経済的価値を生み出すのか」を数値化する工程です。
単なる機能や性能の説明ではなく、
「売上高が年間20%向上する」
「製造コストを年間3,000万円削減できる」
「在庫金額を20%削減し、キャッシュフローに余裕が生まれる」
といった、財務諸表に直結する数値を明らかにするのです。
こうすることで、意思決定者が「投資対効果(ROI)」を即座にイメージできる状態を作り出せます。
マーケティング段階では、「過去の導入実績からすると…」という一般論でも構いません。
しかし、営業段階に移ったら、商談相手となる企業の実態に合わせた数値化を行い「業務改善パートナー」としての立ち位置を確立することが重要です。
拙著『ムリせず、ウソをつかずに1億売れた営業トーク』でも触れていますが、提案書作成のプロセスに商談相手を巻き込むと、受注確度は飛躍的に高まります。
なぜなら、導入効果の数字を一緒に詰める過程で信頼関係が深まり、さらに営業窓口が「自分も参画して作った提案書」という意識を持てば、自然と“推し”の立場に回ってくれるからです。
マーケティングと営業のプロセスに一貫性を持たせることが、組織的な提案力の底上げにつながります。
3つ目の「階層別の提案設計をする」ことは、上記の数値をもとに、経営層・管理者層・現場など、それぞれの関心に合わせたプレゼンテーションを設計していく工程になります。
経営層は、ビジョンやミッションへの貢献度。
管理職は、数字への貢献度。
現場は、使い勝手や価格や契約条件などを重視します。
したがって、「誰に、どの順番で、どの情報を提示するか」という階層別の提案設計が不可欠になります。
もちろん、自社の取扱製品や技術が低額の場合であれば、現場決済だけで通ることもあります。
どの階層で決済が下りるのかを事前に把握することは、提案戦略を立てる上で非常に重要です。
経営層には、企業の長期的な方向性や財務への影響、リスク低減効果を提示。
管理者層には部署の目標達成や業務効率化の具体的効果を提示。
現場には、操作性や導入後のサポート体制、日々の業務負担軽減など、実務に直結するベネフィットを言語化します。
このように、階層ごとに最適な価値を提示できる状態を整えることが、生産財マーケティングを成功に導くための「三大要所」となるのです。
繰り返すと、
✔︎ 顧客の課題の本質を理解すること
✔︎ 価値を数値化すること
✔︎ 階層別の提案設計を行うこと
この3つの視点を押さえることは、生産財マーケティングにおける「価値の構造化」につながり、結果として「売上向上の確度」を格段に高めることができます。
ベネフィット訴求は一見シンプルですが、受注をゴールとしたマーケティング活動―
すなわち営業活動まで含めた戦術設計となると、生産財マーケティングは途端に難易度が上がります。
さらに、ニーズ探索は階層や部門をまたぐため、一筋縄ではいきません。
やるべきこと自体はシンプルであっても、その奥行きは非常に深く、慎重かつ継続的な取り組みが求められます。
いずれにしても、生産財の売上向上策を練り上げるうえで、「価値の構造化」は極めて重要なテーマです。
御社のマーケティング・営業部門は、この「価値の構造化」を共有し、一丸となって顧客への提案価値を最大化する活動に取り組んでいるでしょうか。
