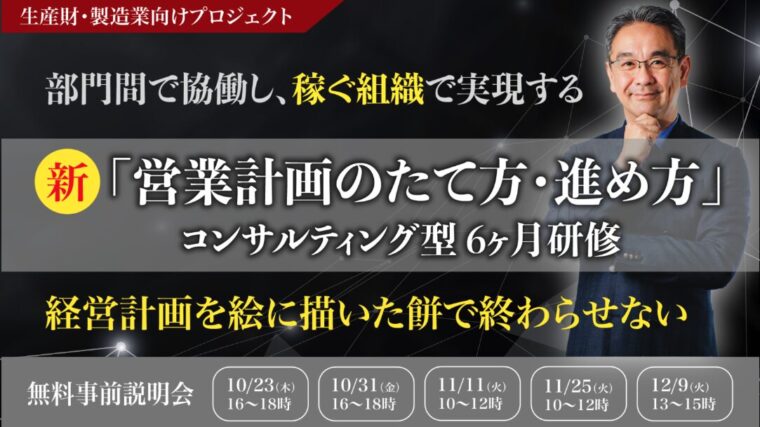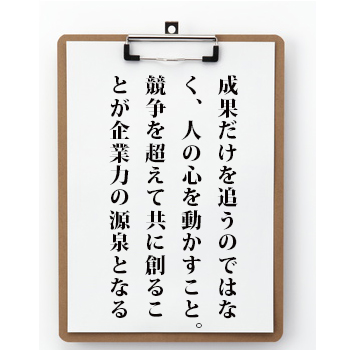
「アメリカ式の逆算方式を推奨したり、日本的な家族経営を賞賛したり、どちらの立場を支持しているのですか?」
読者さんからご指摘を受けて、この数週間に投稿したコラムを読み返すと、確かに混乱される方もいらっしゃるのでは…と感じました。
今日のコラムでその矛盾を解消できるよう、整理整頓してお伝えしたいと思います。
まず、ビジネスで成果をあげるためには、逆算思考が不可欠です。
なぜなら、そもそも経営とは「目的に向かって、限られた資源を最も効果的に配分する行為」だからです。
つまり、目的から逆算して、どこにどの程度のリソースを配分し、どのように戦略・戦術を実行するか―。この逆算思考があってこそ、組織全体が同じ方向へ動き出すのです。
これは、トップマネジメントだけに求められる思考回路ではありません。
ミドルマネジメント層もまた、トップの意向や意思決定を「逆算思考」で捉えなければ、現場への指示は単なる「命令の伝達」に終わり、伝達の精度が落ち、結果として組織の動きが鈍化してしまいます。
逆算思考とは、単に“ゴールから逆にたどる”というテクニックではなく、「なぜこの判断に至ったのか」という“目的の共有”を可能にするための思考様式でもあるのです。
このアメリカ式マネジメントの根幹をなす「逆算思考」は、目標を達成するうえで極めて合理的なアプローチです。
しかし、その一方で、見落とされがちな落とし穴もあります。
逆算思考は論理性の高さゆえに、「人の心」を置き去りにしてしまうという副作用を併せ持っているのです。
目的や数値の達成ばかりが強調されると、メンバーは“駒”として扱われているように感じ、やがて日本人が大切にしてきた精神的支柱との間に、深い違和感を抱くようになります。
私も20代後半から30代前半にかけて、株式公開(IPO)を目指す組織で働いていた時期がありました。
当時は、会社の方針やカルチャーと自分の価値観がすれ違い、言葉にしづらい違和感を抱えていたのを、今でも鮮明に覚えています。
とはいえ、幸運だったのは、「パッケージ・システムを販売する」という押し付け型の営業から、顧客の課題に寄り添い、その解決へ導く「ソリューション営業」へ転換できたことでした。
この転換によって、心の安定を取り戻し、高いモチベーションで仕事に打ち込むことができたことは、懐かしい思い出となっています。
振り返ってみると、目標に向かって仲間と協力し合う「和」だけでなく、顧客や取引先を巻き込んで、共に成長する「和の精神」が、やる気の源泉となり、成果への情熱を高めてくれていたように思います。
こうした経験を踏まえて社会を見渡すと、顧客や取引先を巻き込み、共に成長していく“和の精神”を持つ人には、ところどころで出会うことはありますが…
残念ながら、その精神が企業全体で「共有」されているケースは、ごく少数にとどまっているのが現実です。
おそらく、戦後の社会において「勝つためにあらゆる手段を正当化する」という価値観が、時代の経過とともに少しずつ浸透していったことが、一つの原因だと考えられます。
米軍は日本に二度、原子爆弾を投下し、20万人以上の命を奪いました。
「勝つためには手段を選ばない」という西欧的なスタンスは、1963年の東京地裁判決で、 1963年の東京地裁判決で、民間人への攻撃を禁じた国際法に違反すると判断されています。
それにもかかわらず、社会全体には、いまだにその姿勢を“正当化するような空気”が残っているように感じます。
アメリカ批判のように聞こえるかもしれませんが、そこが本質ではありません。
また、歴史の是非を問うつもりもありません。
ここでお伝えしたいのは、「勝つためには手段を選ばない」という思考が、 成果主義という形を通じて、私たちの働き方や組織の在り方に深く影響を及ぼしてきたという点です。
もちろん、成果を追求すること自体は重要です。
しかし、「勝つために手段を選ばない」という西欧的な発想は、 日本の伝統的な精神とは本質的に相反するものです。
この違いを整理しないまま、無自覚に概念だけを輸入してしまえば、 多くの人が混乱してしまうのも、ある意味で当然のことかもしれません。
個人的な見解ですが、この精神的な混乱こそが、高度成長期を支えてきた“家族主義的な経営”を徐々に弱体化させていった要因の一つではないかと考えています。
この仮説が正しいとするなら、日本企業が競争力を取り戻すためには、まずこの“精神的な混乱”を解消することから始めなければなりません。
そのためには、「目的思考の働き方」と「日本の伝統的思考に基づく働き方」を対立するものとしてではなく、両者を融合させた“より成熟した働き方”として再構築していくことが求められます。
具体的には、現場の目標を「売上・利益」に合わせるのではなく、「顧客の利益」に焦点を置くことで、この新しい働き方を実現できるのです。
言葉にすると簡単に聞こえますが、この思考を組織全体に浸透させるのは決して容易ではありません。
キーエンスのように、粗利益率8割の商品を正々堂々と販売できるのは、「顧客の利益」を視覚化し、理解させる営業手法が徹底されていることにあります。
また、新商品の約7割が“世界初”もしくは“業界初”であるという圧倒的な「企画力」は、営業現場で「勝てるリソース」を供給していると言えます。
このような企業スタンスは、言い換えれば「成果“だけ”を追うのではなく、人の心を動かすこと。そして、競争を超えて共に創ること。」に着眼しているからこそ、実現できる偉業だと言えるでしょう。
「成果」の出発点を「顧客の利益」に置き、その結果として「自社の利益」へとつながるロジックを社内で明確に示すことー。この構造を築くことで、西欧的な逆算思考を取り入れつつ、日本人が大切にしてきた精神的支柱を守ることができるはずです。
御社では、「目的思考の働き方」と「日本の伝統的思考に基づく働き方」の対立を超えた“より成熟した働き方”を、組織として実践できているでしょうか?