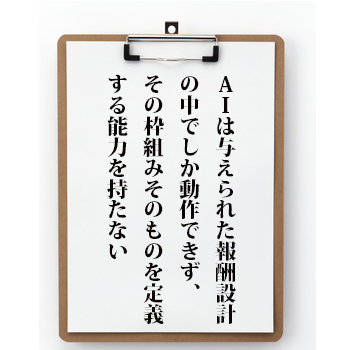
「手段ではなく、目的に焦点を合わせて価値を再定義することが、本当に重要ですね。そもそも手段はAIに代替されつつありますしね。」
先週のコラムを読んだクライアント企業のプロジェクトメンバーから、このような鋭い指摘をいただきました。
その通りです。
実際、弊社のコンサルティングでは、AIを活用してマーケット規模(売上規模)の推定やアタックリストの作成、広告コピーの作成といった作業を、プロジェクトメンバー全員で共有しながら進めています。
こうした一連の「作業」は、今後確実に人間が担う領域ではなくなっていくことを、参加メンバーもはっきりと認識し始めています。
生成AIは、文章作成・デザイン・動画制作・情報収集・分析など、従来は「スキル」や「経験」によって優劣が出ていた領域を、瞬時に代替できるようになってきています。
これを「外圧」と捉えるならば、私たちの組織にとっては大きく変化できる絶好の機会でもあります。
先月公開した第668話「なぜ日本人は逆算できないのか〜日本神話に刻まれた民族のDNA〜」でも触れた通り、日本人は外圧という環境変化が加わることで大きな力を発揮してきた民族です。
主体的に変化を起こすタイプではありませんが、受動的な変化対応能力には非常に優れています。
したがって、AIを外圧とみなし、仕事への向き合い方を一気に変革させていくチャンスと捉えることは、自社を新しいAI時代に適応させるうえで、非常に重要な視点となるのです。
具体的には、外圧そのものを否定したり、逃げたりせずに、積極的に取り込んでしまうことが大事です。
おそらく全社員にこうした布告をすると「自分の仕事がなくなる」と恐怖心を抱く人が一定数いると思います。
しかし、自分たちの仕事がなくなるほど業務のAI化を推し進めていくと、仕事が減るどころか、むしろ新たな業務機会が生まれることに気づかされるはずです。
私たちは過去に似たような経験をしているはずです。
電子メールの普及により、封書の準備や郵送の手間は確かに減りました。
しかし、その一方でメールの件数が増え、結果として業務量はむしろ増加しました。
同様に、インターネットの普及によって国会図書館に足を運ぶ時間は減りましたが、調べられる情報量が桁違いに増えたことで、“より深く考えること”や“適切な取捨選択の判断”が求められるようになりました。
このような現象は、AIでもまったく同じような状況をもたらすはずです。
AIによって作業が自動化されるほど、私たちの仕事は「何を価値とみなすのか」「どこにリソースを投下するのか」という、創造的な思考へと重心が移っていきます。
つまり、これからの仕事とは、「何をするか」ではなく「何に意味を見出すのか」を問われる時代…
言い換えれば、“答えを出す力”ではなく、“問いを立てる力”が求められる時代に移行しているのです。
ここで重要なことがあります。
AIは「過去に存在した価値」を高速で再構築することができます。
しかし、「まだこの世に存在しない価値」や「顧客自身も言語化できていない欲求」を見抜き、新たな意味づけを与えることはできません。
この視点こそが、人間が果たすべき“価値起点の役割”です。
AIは報酬設計に従って動作する存在です。
報酬設計とは、「何を成果とみなすのか」を定義する枠組みです。
囲碁や将棋のように勝敗基準が明確なものや、数学のように正解・不正解がはっきりしている分野では、AIは圧倒的な力を発揮し、高速に最適解へと収束します。
つまりAIは、「どこに向かえばよいか」というゴールと、「どのような出力が望ましいか」という基準が明確である領域において、驚異的な性能を発揮するのです。
しかし、人間や企業が抱える「欲求」や「痛点」には、明確な評価基準があるわけではありません。
むしろ多くの場合、それらは曖昧であり、時に矛盾し、価値観や文化的背景によって常に揺れ動く“動的な概念”です。
✔︎ 自分でも何に悩んでいるのか言語化できていない
✔︎ 誰かに指摘されて初めて、不満や不便といった「痛み」に気づく
✔︎ あるいは、実際に体験してみて初めて、その価値の大きさを理解する
このように、言葉になる前の領域にこそ、本質的な「ニーズの源泉」が存在しています。
このニーズの源泉を突き詰めることで、マーケティングでは新商品開発といった「価値創造」につながり、営業の現場では「キラートーク」の発見につながっていきます。
AIは、目的が明確な作業の遂行には優れています。
しかし、「そもそも何を目的とすべきか」を見出し、新たな価値の枠組みを創造することはできません。
なぜなら、AIは与えられた報酬設計の中でしか動作できず、その枠組みそのものを定義する能力を持たないからです。
目的を見出し、枠組み(=価値)を定義するためには、「問い」を立てる力が必要です。
なぜ?
どうして?
なんか違和感がある…
こうした問いは、正解を求めるものではなく、「意味の可能性」を探る行為です。
人間は問いを立てることで、声にならない感情や価値観を呼び起こし、そこから新たな概念を創出することができます。
また、「どこまで構想を膨らませれば顧客の満足が最大化するのか」といった枠組みを定義する行為は、人間にしかできない高度な思考活動です。
存在しない未来を想像し、構想し、意味づけを与えて価値を創り出す営みこそ、AIには決して代替できない領域です。
前号でも述べた通り、SNSマーケティングやMAツールを使って「手段の最適化」に走ってばかりいると、AIを駆使する同業者に大きく差をつけられてしまいます。
AIはすでに「手段レベルの最適化」を圧倒的な速度と精度で代替する段階に入っており、人間がその領域で勝負しても勝ち目はありません。
だからこそ、これからの時代においては、個人も組織も「問いを立てる力」を備えることが不可欠なのです。
未来の顧客となる人や企業にとって、私たちが提供できる価値とは何か。
この問いを持ち続け、磨き続ける姿勢こそが、AI社会における重要な競争優位性となっていきます。
御社は、自社が提供する価値を「問う」姿勢を大切にしていますか?
