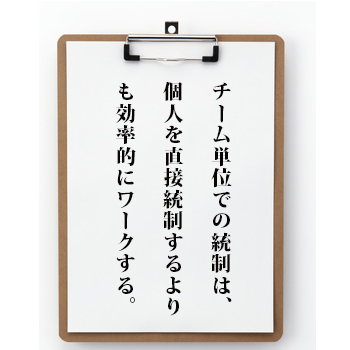
明けましておめでとうございます。
いつも有限会社日本アイ・オー・シーの「とことん本質追求コラム」をご愛読いただき、誠にありがとうございます。
本年も、皆様のビジネスにおける新たな気づきやヒントをお届けできるよう、引き続き質の高いコンテンツ作成に努めてまいります。
どうぞ本年も変わらぬご支援、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
さて、本年最初のコラムは、激変する営業・マーケティングの環境に適応するための組織のあり方を一緒に考察していきたいと思います。
2025年は、日本の政局波乱、トランプ大統領就任による米国至上主義、世界的なインフレによる経済の歪み、AIの社会浸透による労働環境の変化などなど、企業も個人も傍観者でいることは許されない変化が否応なしにやってきます。
一方で、日本の労働者を総括的に見渡すと、周囲との協調性を重んじる力学が働きすぎるためか、変化やリスクに対して積極的に行動することに慎重な傾向があるように感じられます。
これは戦後社会の教育や慣行が大きく影響しています。
組織内部では「横並び意識」が根強く、外部環境が大きく変動しても自分から積極的に一歩を踏み出すことを躊躇してしまう…。
このようなケースは、多くの企業で見られる傾向です。
よく言えば安定思考。悪く言えば事なかれ主義です。
高度成長期において、この体質はうまく機能していました。
しかし、2025年以降の激動期を生き抜くためには、この「安定思考」だけでは乗り越えられない局面が増えていくでしょう。
経営の神様と呼ばれたドラッカーは「組織は絶え間ない変化のために組織化されなければならない」と名言を残しています。
つまり「変化に適応しやすい組織」とは何か。
この課題に今こそ真剣に向き合う時代にきたということになります。
日本アイ・オー・シーにおいても、業績向上をご支援する上で、間接的にこのテーマに取り組んできました。
その一環として、2023年11月には「部門横断チーム」の創設を提唱しました。
しかし、これだけでは何かが物足りない。
そんなことを悶々と考えていたら、正月の深夜2時に飛び起きてしまいました。
ふと頭に浮かんだ「家長制度」が、頭から離れずベッドの中で生成AI「Perplexity(パープレキシティ)」や「ChatGPT」と朝まで格闘してしまいました。
家長制度は、明治政府が富国強兵政策の推進する上で確立した制度です。
家族という単位を通じて、国家のイデオロギーを浸透させるのに、大いに役立ちました。
人の自由や権利を直接制限するのではなく、間接的に個人を統制することができたからです。
ところが残念なことに、有効にワークしたこの家長制度は、第二次世界大戦後に、GHQの手によって解体されてしまいました。
軍国主義の再興を防ぐためです。
ある意味「国力を削ぐ」ために解体された制度ですから、B面から見ればそれだけ強力な統制力をもった制度なわけです。
そう考えると、この「家長制度」の仕組みを再点検し、現代の企業経営に活かすことを考えるべきでは…と、そう直感が働いたのです。
2025年は戦後80年の年です。
いまこそ日本人固有の「強さ」を見直す時です。
富国強兵を強力に推進するための家長制度を企業に転用すれば、「競争や環境変化に強い社員が生まれ、企業が富む」アプローチにつながるはずです。
政府を企業に。
家長をチームリーダーに置き換えてみるのです。
と、ここまで思考が纏まり始めたあと「もしかしたら…」とある疑念が頭をもたげてきました。
家長制度が軍国主義を強力に推進する源になっていたことにGHQは気がついた訳ですから、米国企業がその「家長制度」を応用した組織を作っているのではないか?
という予感です。
調べてみると、その予感は的中していました。
ノーレイティングという評価制度です。
マイクロソフト、アクセンチュア、GE(ゼネラル・エレクトリック)、デロイト、アドビなどが採用し、国内企業でもカルビー株式会社、サッポロビール、スターバックスジャパンが、この制度を取り入れ始めています。
一般的な人事評価制度では、半期~四半期ごとに1回の査定を通じて、従業員のランク付けを行いながら評価を定めていきます。
つまり、会社が定めた基準に照らし合わせて、評価するカタチになります。
一方、ノーレイティングは、従業員のランク付けを行わず、上司と部下の1on1ミーティングなどの機会を設け、個人の目標と達成状況を丁寧に振り返りながら、評価するアプローチです。
個人を直接統制するよりも効率的であるという考えに基づき、チーム単位での統制や評価を実施している点を鑑みると、まさに家長制度の本質をついたアプローチだと見ることができます。
固定化された基準がないため、変化対応がしやすいというメリットもあります。
ある種の安心材料となりかねない「基準」がないので、社員も成果を出すための対策を考え、実行するという臨機応変さが要求されるからです。
上司に負担がかかる仕組みなので、そうそう簡単には移行することはできませんが、経済特区のように、テスト的に一部試験導入することは、有意義な取り組みとなるでしょう。
家長制度をそのまま導入すると、トップダウン型の強権的リーダーシップに陥る懸念もあります。
しかし、家長制度で大切なのは“威圧的な支配”ではなく、“家族を守り、最適な方策を柔軟に示す”姿勢です。
組織内には家長をサポートする“お目付役”や“相談役”を配置し、家長が独走しないようにすると同時に、現場の声を積極的に吸い上げられる仕組みを整えることで有効にワークするでしょう。
日本企業が得意とする「長期的視点」「協調性」を活かしつつも、「スピード感」と「断行力」を補完する枠組みとして機能すれば、2025年以降の急激な環境変化にもしなやかに対応できる組織づくりが期待できるのです。
まずは、賛同してくれるクライアント企業さんと一緒に実証実験に取り組み、研究を重ねたいと思います。(お声掛けください)
御社も、富国強兵ならぬ、「富業強員」策として、この新たな枠組みを探究してみませんか?
