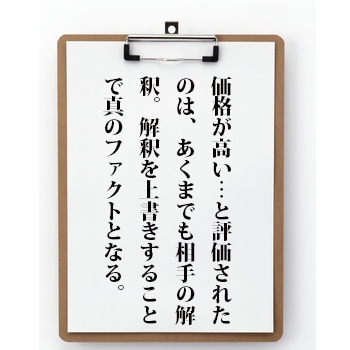
「新商品を売り出しているのですが、価格が高いと言われ成約に至りません。ホームページでも値段は公開していますが、途中で価格を下げても良いものでしょうか?」
読者の方から、ご質問を頂きましたので、コラムでご回答する旨を了解頂きましたので、読者の皆様ともこの問題について共有したいと思います。
さて、先に結論から申し上げると、新商品発売後に、定価を引き下げるのは全く問題はありません。
しかしながら、その前にもっと突き詰めるべきことがあります。
なぜ、商談相手から「価格が高い」と評価されたのか?
という本質的な問題です。
価格が高い…と評価されたのは、あくまでも相手の「解釈」になります。
ファクト(事実)ではありません。
「えっ、でもお客様が明確に発言したので、ファクトですよね?」と、言われそうですが…
発言そのものは確かにファクトですが、「価格が高い」と認識されたのは、ファクトではないのです。
禅問答みたいに思われるかも知れませんが、ここが非常に重要なポイントです。
「価格が高い」という言葉の裏には、必ず“比較の対象”や“期待とのギャップ”が存在します。
つまり、顧客が「この商品には、これくらいの価値しか感じない」と無意識に判断している、ということなのです。
たとえば、10万円の製品が「高い」と言われた場合、その人が頭の中で比較しているのは、同じような機能を持つ5万円の他社製品かもしれませんし、あるいは過去に似たものを2万円で買った経験かもしれません。
つまり、価格が高いかどうかは、商品の価値そのものではなく、「相手の中にある価値基準とのズレ」で起きている現象なのです。
この視点に立てば、すべきことは単に「値下げ」することではなく、むしろ価値の伝え方を見直すことです。
・この商品は、どんな課題をどのように解決するのか?
・その結果、どれほどの時間やコスト、労力が節約されるのか?
・もしこの商品がなければ、顧客はどんな損失を被るのか?
こうした問いにしっかり答えられるメッセージや資料、導入事例を揃えた上で、ようやく価格の検討に入るべきです。
つまり、「価格が高い」と言われたときに真っ先に考えるべきは、価格ではなく「価値の認識にズレがないか?」ということなのです。
ちなみに「価格が高い」と言われた際に、対処方法は2つあります。
一つは、説得する方法。
二つ目は、「納得してもらう環境を設計する方法」です。
前者の“説得”は、営業担当者のコミュニケーションスキルやプレゼン力に大きく依存しますので、組織的な再現性は少々ハードルが高くなります。
サラリーマン時代の先輩で、とても口の立つ人がいました。
「500万円のコンピューターシステムを提案し、相手の社長が”高いなー”と言った時”社長、あれより安いですよ。と駐車場に停まっていたベンツを指さしたのです」
続けて「ベンツで会社はよくなりませんけど、私の提案は会社を良くします!」と言い放し、その場で契約をさせてしまいました。
この話法は、下手をすると相手が怒り出し、商談がまとまらないどころが、会社の評判を落としてしまいかねません。
とても推奨できるやり方ではありませんが、その先輩特有の雰囲気があるからこそ許されるワザなのです。
一方で後者の「環境設計」は、今日のコラムで最もお伝えしたいところの「価値の認識を修正する」アプローチになります。
具体的には、顧客自らが「この価格なら納得できる」と腑に落ちるような前提条件や情報の流れを意図的に整えていくという方法です。
こちらのほうが、仕組みとして再現性が高く、属人的な営業に依存しない戦略になります。
具体的には「比較対象」を提示するアプローチの社内展開です。
あらかじめ自社商品の価値を正しく伝える比較表を用意し、競合製品との違いを“見える化”しておくことで、相手の中にある「不明確な比較基準」を上書きする方法です。
特に、競合との違いが「顧客の痛点」を解消するポイントになることを明確に表現することが大事です。
つまり買わない損失をイメージさせるのです。
「我々の提案を採用しないと、持続的に”痛み”を感じ続けなくてはならない」と感じてもらえれば、受注確度は飛躍的に向上するのです。
本来であれば、営業活動する以前のマーケティング活動(商品企画)の段階で、突き詰めておくべきテーマなのですが、実際に販売スタートしてからでも遅くはありません。
属人的な要素に頼らざるとも高額でも喜んで買ってもらえる環境をぜひ組織的に作っていって欲しいものです。
また、「他社事例」や「ユーザーの声」を活用する方法も有効です。
「他の導入企業が成果を上げている」「価格以上のリターンがあった」という第三者の声は、価格の納得感を支える強力な証拠になります。
これは説得ではなく、“共感”によって自然と心が動く仕組みです。
このように、価格に対する不満や疑念は、単に数字を調整するだけでは解決できません。
むしろ、相手の「比較軸」「判断軸」を丁寧に整えてあげることこそが、本当の意味での価格交渉力なのです。
そして、このような価値の伝え方や環境設計がしっかりできていれば、仮に価格を下げる必要が出てきたとしても、ブランド価値や信頼感を損なわずに、戦略的な価格調整が可能になります。
御社では、組織的な「価格交渉力」の仕組みづくりは出来上がっていますか?
