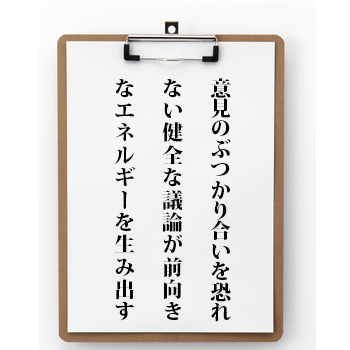
「最初はどうなるかと思いましたが、部門横断チームは社内の雰囲気をガラッと変えて、皆が会社の利益を考えるようになりました」
半年以上プロジェクトをご一緒しているクライアント企業さんから、ようやく安堵の声が聞こえ始めました。まだ「成功した!」というレベルには達していませんが、小さな成功体験は、大きな成長の足掛かりになります。
部門横断チームが業績向上に直結する最大の理由は、「視座の転換」が起きるからです。
具体的には、以前は自部門の目標達成だけを追っていたメンバーが、顧客起点による全社最適の視点で物事を捉える…このような視座の転換が、業績拡大へと組織を導くカギとなるのです。
製造部門は営業を通じて顧客の声を知り、営業部門は製造現場の制約や強みを理解しはじめるーー。
その結果、部署間の「言い訳」や「責任転嫁」が減り、会社として顧客をいかに創造し、今ある課題をどう解決すべきか——両部門が自然と協力しあうようになっていくのです。
さらに、横断チームによる議論を通じて、「本当の課題」が見えるようになります。
たとえば、売上不振の原因が「営業力不足」ではなく「製品コンセプトの市場ズレ」だったり、納期遅延の要因が「製造工程」ではなく「情報伝達のタイムラグ」にあったりします。
こうした「質的なボトルネック」に気づけるのも、異なる視点を持つメンバーが集う横断チームならではの力です。
もちろん、最初から順風満帆に進むわけではありません。
部門ごとの利害や前提がぶつかり、意見がまとまらないこともあります。
しかし、ファシリテーターを会議室に投入すれば、そうした「摩擦」はむしろチームを鍛える肥やしになります。
議論を重ねる中で相互理解が深まり、やがて「共通言語」が定着していきます。
その共通言語こそが、正しい方向づけと的確な合意形成へと導いてくれるようになるのです。
ただし、この共通言語は自然発生的に生まれるものではありません。
顧客と製品をつなぐための視点や価値基準を明確にしたうえで、「共通言語」を意図的に植え付けていく必要があります。
たとえば「コンセプト」と一口に言っても、営業は「独自のアイデアを一言で表現したもの」と理解し、製造は「製品の仕様を定義する要件」と捉えているいて、会話がチグハグになっているケースは多々あります。
こうしたディスコミュニケーション(※)を抑制するために、日本アイ・オー・シーでは、プロジェクト会議で「コンセプト」の定義を徹底的にすり合わせています。
※ディスコミュニケーション:コミュニケーションがうまく機能していない、またはまったく機能していない状態。英語の「dis(否定・欠如)」と「communication(コミュニケーション)」を組み合わせた和製英語です。
コンセプトとは、「誰に対して、どのようなベネフィットを、どのようなシーン(場面)で提供するのか」。そしてその提供価値が「競合と比べて優れているのか」を明確にすることです。
「コンセプト」という言葉が共通言語として機能するようになるまで、認識のすり合わせを重ねていくことが、非常に重要なのです。
というのも、「なんとなく理解しているつもり」で会議を進めてしまうと、後になって方向性のズレや思わぬ誤解が発覚し、プロジェクト全体の足を引っ張ることになりかねないからです。
実際、過去のプロジェクトでも、「言葉の解釈の違い」が原因で仕様の食い違いやターゲットのズレが起こり、大幅な手戻りを強いられたケースがありました。
だからこそ、最初の段階でコンセプトの共通理解を徹底することが、結果としてプロジェクトのスピードと精度を高める近道なのです。
「共通言語づくり」とは、このように「単語」と「概念」の意味を、全員で丁寧にそろえていく作業のことを指します。
「ターゲット」「顧客の痛点」「差別的優位性」といった言葉も、人によって捉え方が微妙に異なります。
これを放置したまま議論を進めると、それぞれが違う方向を向いているのに「同意しているように見える」という、危険な状態に陥りがちです。
逆に、言葉の定義をそろえるだけで、驚くほど議論が噛み合い、意思決定のスピードが上がります。
まさに、「共通言語」はチームを前に進めるための「潤滑油」なのです。
だからこそ、まずこの「言葉のすり合わせ」から始めることが大事なのです。
多少まどろっこしく見えても、これが後の加速のカギになるからです。
また、共通言語づくりは、仲間意識を醸成するうえでも非常に有効です。
長期間にわたり異国を旅していて、日本語を全く話さない状況で、日本人を見かけると嬉しくなる——
そんな感覚を覚えたことはないでしょうか?
共通言語は、ただ情報を伝える手段ではなく、「安心感」や「つながり」を生む土台でもあります。
それがあるだけで、「自分はこのチームの一員なんだ」「一緒にやっていける」という気持ちが自然と芽生えていきます。
この仲間意識が、意見のぶつかり合いを恐れない健全な議論を生み出し、「もっといいものを一緒につくろう」という前向きなエネルギーにつながっていきます。
部門を越えて、顧客視点による「ものづくり」を行い、高収益企業で共通言語は、ただ情報を伝える手段ではなく、「安心感」や「つながり」を生む土台でもあります。
それがあるだけで、「自分はこのチームの一員なんだ」「一緒にやっていける」という気持ちが自然と芽生えていきます。
この仲間意識が、意見のぶつかり合いを恐れない健全な議論を生み出し、「もっといいものを一緒につくろう」という前向きなエネルギーにつながっていきます。
部門の垣根を越えて、顧客視点で「ものづくり」に取り組み、仲間とともに高付加価値経営を創造していくことーーそれこそが、部門横断チームが持つ本質的かつ真の価値なのです。
御社は、部門を超えたチームを作り、健全なる未来を語り合える環境を作られていますか?
