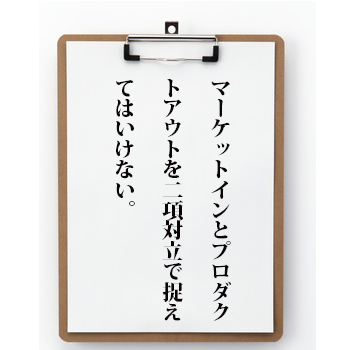
『独自性を打ち出すって、とても重要ですね!』
先日、創業以来はじめてダイレクトメールを発送したクライアント企業さんから嬉しい報告が送られてきました。
これまで同社は創業から50余年「良い製品をより安く販売すること」をモットーに誠実なビジネスを展開してきました。
その姿勢で2020年くらいまでは、それでも成長を実感できていたそうですが…
コロナを境にして、ジリ貧感を抱くようになったそうです。
そこで、満を持して競争力の高い新製品を市場にしたのですが、いざ蓋を開けてみると、反応はゼロ。
想像を超える厳しい現実を味わったそうです。
なぜ、そのような苦境に陥ってしまったのか…
新商品を開発した経緯を伺うと、あるお客様が「オタクの技術を使ったらもっと良いものができるのでは?」と、ふと漏らした一言がきっかけだったそうです。
この手の課題感は、似たようなケースを含めると決して珍しいものではありません。
この原因は「マーケットイン」が大事であるという考え方が、いつの間にか「顧客の言う通りに作ること」だと誤解されてしまっている点にあります。
顧客の声に耳を傾けることは確かに重要です。
しかし、その声を鵜呑みにしてしまうと「マーケットインの悪夢」が始まります。
そもそも、その顧客は、1社にだけニーズを話してくれているのでしょうか?
もしも、複数社に同じようにニーズを話していたら、どうなるのでしょうか?
答えは火を見るより明らかです。
本来であれば、競争力の高い商品を生み出そうと努力していたのに、結果的に他社と同じような商品を作ってしまっていたということになりかねません。
”差別化”ではなく“同質化”の罠に、自らはまってしまうー。
そうです。マーケットインは同質化に陥るリスクがあることを忘れてはならないのです。
「同質化の罠」に陥いると、結果として価格競争に巻き込まれてしまいます。
このとき被る損害は、単に「粗利益」が削られるだけではありません。
営業部門の「モチベーション」までもが奪われてしまうのです。
これまでの経験から言えば、営業部門が「うちの商品には競争力がない」とモチベーションダウンしている企業の割合は、感覚的に8割を超えています。
繰り返しますが、これは「マーケットイン」という単語を、深く理解しようとする努力を怠ってしまった結果です。
マーケットインとは、「顧客のニーズを聞いて、その解決技術や製品を作りだすこと」ではありません。
顧客がまだ言語化できていない本質的な課題や、ニーズの裏側に潜む根源的な欲求を見抜き、そこに対して独自の解決策を“プロダクトアウト”していくことこそが、本当に重要な姿勢です。
そう考えると、「マーケットイン」と「プロダクトアウト」を単なる対義語として扱うのは、本質を見誤っていると言えるのではないでしょうか。
また、「プロダクトアウト」という言葉も、いきなり登場させると混乱を招く原因となります。
本来の「あるべき姿」は、顧客の本質的な課題に気づき、それを根本的に解決するアイデアを考え、そのアイデアを実装する「商品」を開発することです。
つまり、
・顧客の本質的課題に気づくこと(≒マーケットイン)
・課題解決アイデアを考えること(≒コンセプト開発)
・アイデアを実装する製品を開発すること(≒プロダクトアウト)
これは一連の業務フローであり、本来は分断されるべきものではありません。
マーケットインとプロダクトアウトは、「対立構造」を持つ対義語ではなく、むしろ両者は補完関係にあり、どちらか一方では不十分なのです。
顧客課題に対する深い理解と、それを具現化する技術やアイデアの接続がなければ、どれだけ優れた技術力があっても「響かない商品」になってしまいます。
マーケットインとプロダクトアウトを二項対立で捉えるのではなく、 「マーケットインの視点で課題を見抜き、プロダクトアウトの姿勢で解決策を創造する」という“統合的思考”こそが、これからの時代に求められるアプローチです。
この姿勢を徹底できる企業こそ、商品そのものに「営業力」を内包させることができるのです。
実際、冒頭で紹介したクライアント企業も、商品に営業力を組み込んでいたからこそ、DMを通じてその価値を的確に伝え、大きな反響を得ることができました。
本質的な課題を抱えたビジネスにおいては、できるだけ「川上」の段階で解決策を講じておくことが重要です。
企画段階で間違いに気づいたのなら、企画をやり直せば済みます。
製品企画がズレていたなら、企画書を書き直せば済みます。
仮に商品開発が進んでしまっていても、機能や仕様を再調整することで、軌道修正は可能です。
しかし、「商品に営業力を内包させる」ことを忘れたまま営業活動を始めてしまったら——
・開発のやり直しにかかるコスト
・製造工程の見直しによるコスト
・売れない期間の営業コスト(広告費・交通費・人件費 など)
これら膨大なリソースがムダになり、最悪の場合はゼロからのやり直しを迫られることになります。
もちろん、開発まで遡らなくても、「営業の切り口」を工夫することで軌道修正できるケースもあります。
それでもやはり、商品企画の段階(川上)で、“営業力を内包した商品”を設計しておくことに越したことはありません。
御社は、マーケットインとプロダクトアウトを二項対立で捉えず、総合的な思考によって、商品企画を実施していますか?
