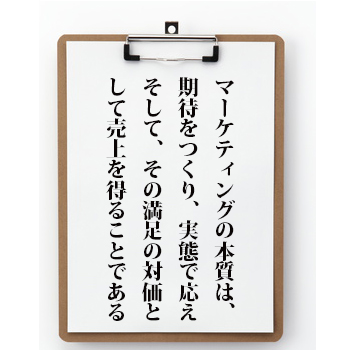
本日のコラムは、いつもとは少し趣向を変えてお届けします。
テーマは、7月25日に華々しくグランドオープンした「ジャングリア」について——
タイトルは「ジャングリアの危機から学ぶ“マーケティング”の本質」です。
「危機」という表現に対し、大げさだと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、Googleマップの口コミには、オープン直後から「期待はずれ」「がっかり」「騙された」といった厳しい評価が相次いで投稿されていました。
私(藤冨)も現地視察に赴きましたが、率直に申し上げて、レビュー通りの“負の感想”を抱かざるを得ませんでした。
まず、入場前からトラブルに見舞われました。
入場ゲートで必要となる「アプリ」が起動せず、QRコードが表示されないという障害が発生したのです。
たまたま事前に「QRコードのスクリーンショット」を準備していたため、なんとか入場できましたが、準備していなかった来場者の多くは、ゲート前で立ち尽くしていました。
ようやくゲートを通過すると、数多くのスタッフが笑顔と拍手で出迎えてくれました。
その光景に、ゲストたちの期待感は一気に高まっていったのですが……
その期待は、ほどなくして裏切られます。
アトラクションに乗るための「整理券」もアプリ経由で取得する仕組みだったのですが、アプリが起動せず、多くの来園者が立ち往生。
園内のあちこちでスマートフォンを片手にイライラしている人たちで埋め尽くされていました。
スタッフに状況を尋ねたところ、「皆さんが一斉にアクセスしたためです」との説明。
しかし、森岡毅氏は「高等数学を駆使した需要予測」によって、来場者数を1%の誤差で予測できるとされてきた人物です。
であるならば、想定アクセス数も把握できていたはず。
この“ファクトの矛盾”は、顧客に混乱を招き、やがては不信へとつながってしまいます。
その“嫌な予感”は、園内を歩くほどに、確信へと変わっていきました。
誤解のないよう申し添えておきますが、私は決して森岡氏やジャングリアそのものを批判したいわけではありません。
むしろ、森岡氏の構想力や行動力には敬意を抱いていますし、個人的にも応援したいと考えています。
だからこそなおさら、ジャングリアの運営責任者には、こうしたネガティブな印象を真正面から受け止め、誠実かつ的確な改善策を講じてほしいと願っています。
今回の事例は、とことん本質を追求するこのコラムの読者にとって、“学びの宝庫”だと私は捉えています。
ぜひ、ご自身のビジネスの参考にして頂ければと思います。
それでは本題に戻りましょう。
開業からわずか2日間で、Googleマップの口コミに311件もの悪評を集めてしまった理由を、順を追って整理していきたいと思います。(SNSによると400件以上あったとの投稿もあります)
まず冒頭で述べた通り、1点目は「システム障害」は設計ミスによるものです。
想定される同時アクセス数を見込んだ上で、それに見合ったサーバー環境を構築すべきでした。
おそらく、回線の維持コストが高額になることを懸念し、多少の不具合は許容できると判断してしまった可能性があります。
次に2点目は、期待値を上げすぎたことで、ゲストが「裏切られた」と感じてしまった点です。
たとえば、メインアトラクションの「恐竜に追いかけられる”ダイナソー サファリ”」は、事前のプロモーション動画では、恐竜から追いかけられる!と宣伝していました。
しかし、実態は、“追われている体(てい)”の演出に過ぎず、ジープが急発進する仕組みで逃走感を演出しているだけでした。
また、“圧倒的な景色が楽しめる”とうたわれた「鳥かごのレストラン」も、実際の高さは推定3〜5メートル程度。そのスケール感のギャップに落胆した人が多かったことは、後の口コミ評価からも明らかです。
拙著『ムリせずウソをつかずに1億売れた営業トーク』でも述べましたが、「セールストークの火種」が強すぎると、それが炎上の引き金になることがあります。
今回の「ジャングリア」は、まさにその典型例と言えるでしょう。
3点目は「体験価値の乏しさ」です。
私は幸いにもメインアトラクションを体験することはできましたが、来場者の中には1つも体験できず、ただ広い公園に来ただけ…という印象を抱いた人が続出していたことがSNSで共有されていました。
ちなみに、事前にプレミアムチケットが販売されていましたが、販売初日はサーバーがパンクしていたようで、接続できず。夜間に再接続を試みたものの「売り切れ」という状態でした。
整理券も上述の通り、アプリが起動せずに入手できない状況に。
仕方なく、長蛇の列に並ぼうとするも、5時30分待ちという状態でした。
開業直後に問題が生じるのは、ある程度は仕方のないことです。
しかし重要なのは、こうした課題や問題にどう向き合い、改善策を講じて顧客の信頼を取り戻すかという姿勢です。
このケースは、新商品や新規事業を推進する上で、多くの学びを得られる教材でもあります。
他人事とせず、「自分が運営責任者だったらどう対処するか?」と真剣に考えることが大切です。
こうした思考の訓練こそが、いざという時の“適切な対処力”につながります。
藤冨も、自分なりに対策案を考えてみました。
【1点目】システム障害への対策
仮に「回線容量不足」が主因だったとすると、対策としては費用負担の大きい「回線容量の増設」だけでなく、「同時アクセス数を抑える設計思想」にも目を向けるべきです。
回線費用は、アクセス数が増えるほど高額になります。
繁忙期に合わせてスペックを上げると、平時はオーバースペックとなり、コスト効率が悪くなります。
そのため、ありがちな“中間を取る”という発想ではなく、そもそも同時アクセス数を抑える設計が必要です。
たとえば、アナログの園内マップにQRコードを設置し、整理券の取得時のみアクセスさせれば、常時接続を防ぐことができます。
また、待ち時間の案内も、アプリに5分ごとに自動配信する仕組みにすれば、ユーザーがアクセスする「上り通信」を減らすことが可能です。
このように「システム設計の思想」を変えるだけで、回線負荷を抑えつつ、ストレスのない体験を提供することは十分可能なハズです。
藤冨は20代の頃、システム会社の営業をしていました。
「それは無理です」と言われた案件でも、「こうすればできるのでは?」と提案し、理想的なシステムの実現してきた経験を何度もしてきました。
プログラミングの知識がなくても、課題に真摯に向き合えば、解決の糸口は見つかるものです。
専門外だからといって尻込みせず、「この課題をこう解決する方法はないか?」と柔軟に発想することが重要です。
【2点目】期待値と実態のギャップへの対応
期待値を下げるか、実態を引き上げるか、どちらかの対応が求められます。
まずは、アトラクションのPRやイメージ画像を実態に合わせて見直し、誤解を招く表現を排除することが必要です。
また、設備投資に余力があれば、実態の方を期待に近づけていく改善も必要です。
たとえば、「恐竜が追いかけてくる」という体験をよりリアルにしたいのであれば、振動や音響による足音の演出を加えるといった工夫も可能なハズです。
このような検討を行うためには、部門横断型のチームをつくり、あらゆる改善案をテーブルに並べて議論すべきです。
【3点目】体験価値の向上への対応
当たり前のことですが、入場者数を制限し、一人一人の体験価値の向上を図ることは、口コミ社会が浸透した今、最も意識しなければならないことです。
雨天対策や日陰の場所が乏しいこともSNSで指摘されていましたが、一人一人のネガティブなクレームの「ファクト」だけに着目し、的確なる改善策を打つことが大切なのではないでしょうか。
「ジャングリア」を運営するジャパンエンターテイメントの株主であり、主要な推進役でもある森岡毅氏率いる「刀」は、24億円の赤字が指摘されており、厳しい財務状況下でプロジェクトを推進せざるを得ない状況だと推測されます。
飛躍しようとする瞬間に訪れる大きな壁の出現は、経営者ならば、一度や二度は必ず経験する困難です。
このような局面で、目先の売上利益をとろうとする経営者は、さらなる地獄を味わい、先を見据えた本質的な対策を打ち続ける経営者は、不思議なほど復活の道筋を見出すものです。
逆境の中でこそ、経営者の手腕や胆力が試されます。
業種は違えど、ビジネスの本質は同じです。
「期待をつくり、実態で応える。そして、その満足の対価として売上を得る」
これこそがマーケティングの本質なのです。
御社では、どのような期待をつくり、どのように実態で応えていますか?
追伸
残念ながら、ジャングリアの運営部はGoogleマップに書き込まれていた311件のレビューを、大幅に削除してしまいました。
これは“証拠隠滅”と言わざるを得ず、消費者の信頼をさらに損ねる行動となりそうです。
ジャングリアの運営部には、ぜひ下手な対処に知力を使うのではなく、真摯な改善対応に尽力してもらいたいと心の底から願っています。
今後、どのように信頼を回復していくのか——
その姿勢を、引き続き注視していきたいと思います。
