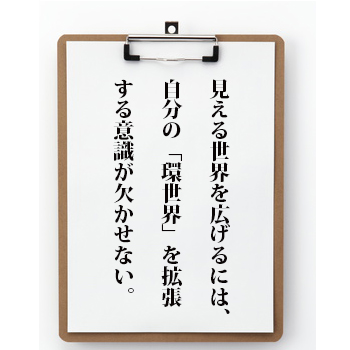
「前回のコラム『顧客のお困り事を掘り下げる視点』は、私も参考になりましたよ。ただ、実際に指導して実践につなげるのは難しくないですか?そもそも、相手の業務に興味を持っていないと、事実を掘り下げること自体が難しいですよね」
仲間のコンサルタントと酒席を共にしたとき、そんな話題で盛り上がりました。
さすがにデキる人は、一言で本質を突いてきます。
実際、その通りです。
どれほどテクニックを知っていても、聞き手に「知りたい」という強い内発的動機がなければ、核心を突く情報を引き出すことはできません。
さらに言えば、そもそも核心情報へつながる「入り口」すら見えないのだと思います。
情報の入り口とは、表面に現れている「現象」のことです。
核心は常に「内面」にあり、その内面を覆う「現象」に興味や関心を持たなければ、ただ通り過ぎてしまいます。
要するに、核心を掘り下げる以前に「気づけるかどうか」が問われるのです。
例えば、顔色の悪い人が道端に座り込んでいたとします。
ある人は「少し休めば良くなるだろう」と横目で見て通り過ぎます。
一方で、医学的な知識を持つ人は、周囲の状況や本人の苦痛の様子、さらには手足の細かな震えに気づき、緊急対応が必要だと判断して救急車を要請しました。
知識の有無によって、見える世界は大きく変わるのです。
ファクト主義を追求するために生物学者から生理学者へと転身したユクスキュルは、その著書「生物から見た世界」の中で、このことを「環世界」と表現しました。
環世界とは、生物種が知覚し、行動できる物理的・意味的範囲です。
これは、環境の一部を「意味あるもの」として抽出した主観的な世界を指します。
ユクスキュルは「客観的な環境という世界は存在しない」と主張し、生物の種によって見えている環境が異なることを実証的に示しました。
これは、人によって見える世界が異なるため、事実やその重要性の捉え方も変わってくることを示唆しています。
私たちのビジネスの世界を振り返ってみても、この仮説は見事に当てはまります。
例えば、ある倉庫に在庫の山が積み上がっていたとしましょう。
財務担当者であれば、「在庫回転率はどのくらいか」「キャッシュフローに悪影響はないか」と関心を寄せるかもしれません。
営業担当者であれば、「こんなに売らなければならないのか」「白地リストと突き合わせて販売計画を立てなければ」と焦りを感じるでしょう。
仕入担当者であれば、「適正に発注できているのか」「需要予測の方法は妥当か」「取引先との発注量の交渉は適切か」と疑問を抱くかもしれません。
同じ“在庫の山”を見ても、立場や知見によって見える景色は異なり、注目するポイントも変わってくるのです。
その現象への関心を起点に、深く切り込む質問が、核心を突く情報を掘り起こすのです。
理解を深めるために、もう一度ユクスキュルの「生物から見た世界」に戻ってみましょう。
ユクスキュルは、ダニを観察し、彼らが認識している世界はわずか3つの要素に限られていると指摘しました。
ダニは木の上でじっと動物が通るのを待ちます。
そして、動物が真下を通った瞬間、落下します。
この時に反応しているのは視覚ではなく、動物から発せられる酪酸の匂いです。
無事に着地すると、次は体毛のない部分を探し回り、吸血しやすい場所へと移動します。
そして体温を感じ取った瞬間に吸血を始めるのです。
ダニは、いかに多彩な環境に囲まれていても、「酪酸の匂い」「体毛」「体温」の3つだけを手がかりに世界を認識しているのです。
ここで重要なのは、ダニが極めて限られた「感覚の世界」に生きていることです。
動物でなくても酪酸の匂いに反応すれば落下してしまい、体温に似た熱を感知すれば、それが血液でなくても吸血を始めてしまいます。
仮にそれが毒であっても…です。
つまり、ダニは多様な動物の存在を認識できず、血液と似た液体を区別することもできません。
生物は知覚できる範囲でしか世界を理解しておらず、その枠組の中で行動が決定されてしまうのです。
ユクスキュルの「生物から見た世界」では、イソギンチャクや犬、ヤドカリなど多様な生物を例に挙げ、それぞれに固有の「環世界」が存在することを実証しています。
この原理は、生物に限らず、私たちビジネスパーソンにも当てはまり、「環世界」を広げるための重要な示唆を与えてくれます。
要するに、見える世界を広げるには、自分の「環世界」を拡張する意識が欠かせません。
それは言い換えれば、自らの生存条件…すなわち学びや経験の幅を広げることに他ならないのです。
どこに潜んでいるかわからないニーズ、それが「潜在ニーズ」です。
消費財マーケッターであれば、人間のもつ感情、本能、行動原理などを深く理解する必要があります。
一方、生産財マーケッターに求められるのは、企業を深く理解することです。
顧客となり得る相手のビジネスモデル、管理会計や生産技術など経営の仕組みにまで目を向けてこそ、核心を突く情報ー潜在ニーズを発掘することができるのです。
知らない世界に飛び込むことは、不安になることもあるでしょう。
「そんなことも知らないのか!」とバカにされたり、無知をさらけ出してしまうのではないかと恐れる気持ちが芽生えるかもしれません。
しかし、実際には「知らない」と認める勇気こそが、成長の第一歩です。
むしろ相手にとっては、自分の領域に関心を持ってくれたこと自体が嬉しく、誠実に教えてくれるものです。
そうしたやり取りの中で、顧客や市場の価値観や行動原理が垣間見え、自分の「環世界」が確実に広がっていくのは、間違いありません。
御社でも、「環世界」を広げる社内文化を意識的に育んでみてはいかがでしょうか。
新しい領域に一歩踏み出す勇気を称え合い、異なる視点や知見を持ち寄る風土があれば、組織全体の思考の幅は大きく拡張していくはずです。
