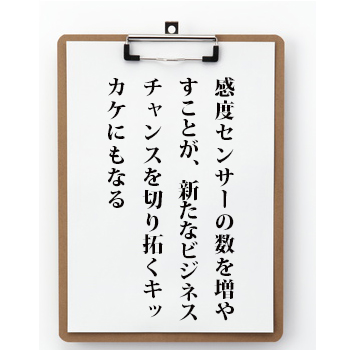
「今回のコラムは、すごく興味深かったのですが、藤冨さんが、いつも言っている”解像度を上げる”という視点との関連性がよくわかりませんでした。見える世界を広げると解像度が上がる…ということでしょうか?」
先日、プロジェクトをご一緒している企業のご担当者から、このようなご質問をいただきました。
非常に重要なポイントなので、その際にお伝えした内容に補足を加え、ここで整理しておきたいと思います。
まず、読者の皆さまにとっては「解像度を上げる」という表現が突然出てきたかもしれませんので、その背景からご説明します。
日本アイオーシーが伴走する「商品の魅せ方を変えて売上を拡大していくプロジェクト」では、常に「お客様はなぜこの商品を購入するのか?」というシンプルな問いを徹底的に掘り下げていきます。
一人のお客様の購入理由は、他の人にも共通するものなのか。
共通するなら、どのようなセグメントで括れるのか。
さらに、そのセグメントをターゲットリストとして収集したり、接点を持つ手段はあるのか。
―このように突き詰めて考えていきます。
つまり、購入理由の本質を明らかにし、同じ動機を持つであろう人たちに、私たちの提案を届けるプランを設計する。ここで成功と失敗を分ける大きなポイントが「共通の購入動機を発掘できるかどうか」なのです。
もし購入動機の見極めを誤れば、無駄な広告費を垂れ流し、成果の上がらない営業活動に時間とコストを費やし、さらには広告担当者や営業スタッフのモチベーションまで低下してしまいます。
だからこそプロジェクトでは「その理由は本当にターゲット層に響くのか?」という視点で解像度を高めていきます。
会議室だけで議論するのではなく、実際に顧客のもとへ足を運び、購入理由やその背景、前後関係といった文脈(コンテキスト)を、構造的かつ立体的に理解しようと努めるのです。
この「購入理由の文脈の解像度」が高まれば、次に展開する販売促進や広告、すなわち「反響営業」において非常に強力な武器となります。
私たち日本アイ・オー・シーは、さまざまな業種・規模のプロジェクトに携わっていますが、会議室で聞いた「購入理由」と、実際に顧客にヒアリングして得られる内容とでは、大きく異なることがほとんどです。
むしろ、差がない方が例外であり、ほぼ100%の確率で売り手は買い手の購入理由を正しく把握できていません。
だからこそ、会議室で「購入理由は何だろうか?」と議論しているときに、必ずといっていいほど「解像度を高めないと見えてこないな」という発言が出てくるのです。
もう30年近く前の記事(日経新聞「私の履歴書」)なので記憶はあいまいですが、東京ディズニーランド2代目社長の故・高橋政知氏は、パーク内を歩きながら来園者の表情や雰囲気を直接観察し、ゲストの満足度や自分たちの仕事の成果を肌で感じ取っていたといいます。
まさに「解像度を高める」姿勢そのものです。
高橋氏は形式上は2代目社長でしたが、私は実質的には創業社長と同じマインドを持っていたと感じています。
というのも、氏は東京ディズニーランドの用地取得から携わった立ち上げメンバーであり、気性の荒い漁師たちを相手に「漁業権放棄の補償交渉」をたった一人で行ったほか、千葉県との遊園地用地払い下げ交渉、本家ディズニーとの交渉など、開園に向けた数々の難題を乗り越えた第一の立役者だったからです。
きっと自分の子供のようにパークが可愛かったのでしょう。
休日でもパークを訪れて、顧客の満足度を肌で感じ続けようと努力した経営者でした。
お客様アンケートの集計を眺めて、満足度を感じるとることも大切ですが、やはり肌で感じることのほうが解像度は高まります。
こうした「顧客が喜ぶ理由」や「購入する理由」の解像度を高めていくと、自分たちのやっている仕事が、社会の喜びや発展に寄与していることが実感できていきます。
日本アイ・オー・シーでは、これが「波及する原点」だと捉えています。
さて、解像度を高めることはご理解頂けたかと思いますが、それと先週のコラムの「視野を広げる(≒環世界を広げる)」との関係性はどこにあるのでしょうか?
端的にいうと、視野を広げることは、“問いの仮説を増やす”ことであり、解像度を高めることは、“その仮説を深く検証する”ことです。
つまり、まずは視野を広げて「もしかすると、こういう購入理由もあるかもしれない」「こういう人たちにも刺さるのではないか」という仮説の候補をたくさん見つけます。
これが“環世界を広げる”という段階です。
しかし、ここで止まってしまうと、ただ仮説を並べただけの「表層的な理解」にしかなりません。
そこで必要になるのが、「本当にそれは事実なのか」「どんな文脈でそうなったのか」「どのような条件下で共通しているのか」と、仮説一つひとつを丁寧に掘り下げ、確度を高めていく作業です。
これが“解像度を上げる”ということです。
言い換えるなら、
・視野を広げることは、興味関心を示すポイントや購入理由の“幅”を広げること
・解像度を上げることは、上記の一つ一つの仮説または事実関係の“深さ”を掘り下げることです。
両者は別物でありながら、相補的な関係にあります。
視野を広げなければ、新しい可能性や切り口に気づけません。
一方で、解像度を高めなければ、せっかく見つけた可能性も“本当に響くのかどうか”を見極めることができません。
たとえば産業財の場合、窓口となる担当部署の購入理由、関連部署が感じる導入メリット、そして経営層が受け取るメリットなど、購入理由や導入後に得られる効果には、それぞれ異なる文脈が存在します。
その文脈を「肌感覚」として捉えるには、まず窓口担当部署の業務に興味を持ち、課題感を自分ごとのように感じられる「環世界」を持つことが重要です。
さらに、関連部署への感度を高めたいのであれば、業務の流れやビジネスプロセス全体に関心を寄せることが欠かせません。
加えて、経営層への感度を高めるには、企業経営そのものへの理解と関心を深める必要があります。
感度を高めることは、解像度を高める入り口のなるからです。
この感度センサーの数を増やすこと、つまり視野を広げて「環世界」を拡張させることが、商談成約率を向上させるだけなく、さらに新たなビジネスチャンスを切り拓くきっかけにもなります
御社では、視野を広げる訓練と解像度を高める訓練を、組織的に行なっていますでしょうか?
