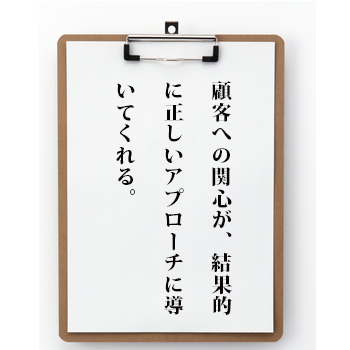
「(製造業の)マーケティングを学ぶのに、良い本があれば紹介してください。これまで読んできた本はコンシューマ向けのノウハウが多いと感じたので、生産財に特化した本を読んでみたいです」
先日、クライアント企業のプロジェクトメンバーから、このような相談を受けました。
確かに、書店やネットで目にする「マーケティング本」の多くは、消費者行動を前提にしたBtoC(コンシューマ向け)のノウハウが中心です。
私自身も数年前に「生産財」「マーケティング」といったキーワードでAmazon検索を行い、ヒットした本を片っ端から購入しました。
しかし、その多くはアカデミックな研究書であり、実務に直結する内容はほとんどありませんでした。
残念ながら、生産財特有の「購買意思決定プロセス」や「意思決定者の多層構造」「営業とマーケティングの一体運用」を実践的かつ体系的にまとめた本には、いまだ出会えていません。
そのため、率直に「残念ながら一冊で学べる決定版はありません。やはり乱読と実践を繰り返すことが最も効果的です」とお伝えしました。
そもそも一般的なマーケティング本の多くは「販売」に焦点を当てています。
しかし、本来のマーケティングの役割は、「価値を創り出すこと」と「その価値を伝えること(売ること)」の二つを担っています。
特に製造業の場合、「価値を創ること」の比重が非常に大きくなります。
技術力や品質、耐久性といったハード面はもちろん、導入後の運用効率や安全性、さらにはアフターサービスまで含めて“価値”と見なされるからです。
したがって、消費財のように「イメージ訴求」や「感情喚起」だけで購買につながるわけではありません。
また、購買の意思決定に関わる人物も多層的です。
現場の担当者、管理職、経営層―それぞれが異なる視点で「価値」を評価します。
そのため、マーケティング活動は単なる広告宣伝や販促ではなく、営業現場と密接に連動させながら、各階層に響くメッセージを届ける設計が不可欠になります。
日本アイ・オー・シーが「波及営業」という販売・マーケティングノウハウを用いて、クライアント企業の成果につなげようとする中で直面した大きな壁が、まさにこの「生産財固有の意思決定構造」と「売りモノと売り方の密接な関係」でした。
生産財の購買は、現場担当者の利便性や作業効率の改善といった視点だけで決まるわけではありません。管理者層は安全性や標準化、経営層は投資対効果や全社的な競争優位性を重視します。
つまり、一つの製品を導入するにも、複数階層の利害や判断基準が複雑に絡み合うのです。
その全体を見渡した上で「誰に・どのような言葉で価値を伝えるか」を設計しなければ、成果には結びつきません。
さらに「売りモノと売り方」は切り離せない関係にあります。
優れた製品であっても、営業のアプローチが従来型の“価格・納期訴求”にとどまれば、すぐに価格競争に巻き込まれてしまいます。
逆に、売り方を工夫して“経営課題の解決策”として提案すれば、同じ製品でも粗利を確保しながら採用される可能性が高まります。
消費財とは、まったく次元の異なる「思考」が必要になるのです。
だからこそ、実践知から培ったノウハウを抽象化し、さらに形式知として整理・体系化していく作業が不可欠だと考え、私は今も試行錯誤を重ねながら、体系化に挑み続けています。
思い返すと面白いもので、20代のITシステム営業マン時代からすでに、「生産財固有の意思決定構造」と「売りモノと売り方の密接な関係」に取り組んでいたことを思い出します。
とりわけ意思決定構造については、扱っていた商材が「情報システム」だっただけに、その影響範囲は非常に広範でした。
現場・管理者・経営層といった“タテの構造”だけでなく、「営業」「経理」「人事」などの部門にも影響するため、“ヨコの構造”にも深く関わらざるを得なかったのです。
窓口担当者だけでは「受注確度」が見えないため、キーマンを引き寄せるトークや、関連部署を巻き込んで味方につける作戦など、現場で手探りで進めてきたアプローチもありました。
また、生産財の場合は、商談中に「この仕様を実現しないと購入できない」といった要望が出されたりもします。
この時、「その仕様を実現しなくても、このような使い方なら、御社のご意向はカバーできますよ!』と営業サイドだけで話をまとめたり、他の顧客にも提案できそうな市場性のある要望なら、開発に掛け合って、「これだけの市場があるから、開発してほしい」と依頼したりもします。
このサジ加減のバランスが、社外・社内の信頼関係を大きく左右します。
顧客からすれば「きちんと要望を汲み取ってくれる会社かどうか」が判断基準になりますし、社内の開発や製造部門から見れば「営業が勝手に約束して無理を持ち込んでいないか」が気になるところです。
ここで重要なのは、単なる御用聞きや橋渡し役にとどまらず、営業が「経営視点」を持つことです。
担当者目線の顧客の要望は、経営陣から見れば不要と考えることもありえます。
だからこそ、そのまま鵜呑みにせず、なぜその仕様が必要なのか、その背景にある業務課題や経営上の狙いを把握したうえで、最適な落としどころを提案する。
その姿勢が、顧客からも社内からも「頼れる存在」として認められる条件になります。
こうした活動は、振り返ってみると、意外と的を射た取り組みだったことに驚かされます。
手前味噌ではありますが、顧客の業務プロセスの生産性やシステムそのものに強い関心を持っていたことが、結果的に正しいアプローチへと導いてくれたのだと感じています。
繰り返しになりますが、マーケティングの出発点は常に「顧客」です。
顧客を起点に「価値をつくり」、その価値を「伝える」。この一連の活動こそがマーケティングの本質です。
冒頭で「乱読と実践をオススメする」と述べたのも、この考えに基づいています。
大切なのは、手法を学ぶことよりも、顧客を徹底的に学ぶこと。
そこに、製造業におけるマーケティングの本質があるのです。
御社では、顧客を学ぶ慣習を大切にしていますか?
