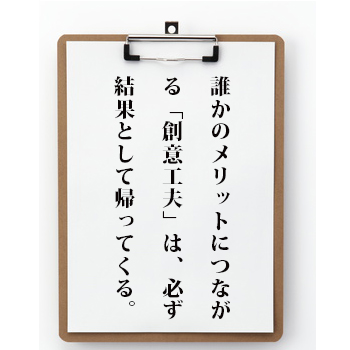
「創業者の知恵は、本当にすごいですよね」
先日、プロジェクトをご一緒している社長さんと一献傾けながらお話をしていたとき、同社の創業社長の話題になりました。
同社は、他社の追随を許さない優れた技術・製品力を保持しながらも、創業から50年以上経った今なお、イノベーションへの探究を追求している素晴らしい企業です。
企業文化が脈々と受け継がれている様子を伺うと、バトンタッチされた社長の姿勢次第で、DNAは法人にも確かに宿り続けるのだと気づかされます。
時代が変わっても企業の芯を守り抜くこと。
一方で、時代の変化に合わせること。
柔軟さと一貫性、この二つを両立させることこそ、永続企業の条件ではないでしょうか。
そして、同社における一貫性の本質は、まさに「差別化」にあります。
製品の差別化のみならず、販売においても「差別化」を常に模索されています。
今回のコラムでは、上述した創業者の「差別化の原点」について、酒席で伺った話をご紹介したいと思います。
同社の創業者は、小学5年生のときに野菜の行商をしていたそうです。
競争相手が多く、すぐに値引き合戦になり利益が出なくなる状況を見て、「競争があるから儲からない。ならば競争をなくせばいい」と考えたといいます。
齢11歳の子どもとは思えない発想です。
そこで少年が取った行動はこうでした。
周りの行商人は町の入り口の低地から売り始める。ならば自分は、あえて奥の高台から売り始めよう―。
重たい荷物を担いで坂道を登るのは大変なため、誰もやりたがらなかったのでしょう。
その結果、競争相手のいない場所で野菜を売ることができ、値切られずに済んだため利益を確保できたのです。
驚くのは、それだけで満足しなかったことです。
翌年には道端の花を束ねて客にプレゼントする、という工夫を思いつき実行したのです。
当時の主婦は多忙を極め、仏壇の花を買いに行く時間すら惜しかった背景もあり、そのアイデアは村人に大変喜ばれたとのこと。
まさに「顧客の痛点」を突いた「販売の差別化」でした。
このお話を伺った帰路、私も少年時代の思い出が頭に浮かんできました。
手前味噌ですが、私の商売の原点も小学5〜6年の頃でした。
当時、祖母と一つ屋根の下で暮らしていましたが、無条件でお小遣いをくれるような人ではありませんでした。
とても優しい祖母でしたが、「お金は何かしらの仕事を手伝った対価として受け取るもの」という感覚を、私に身につけさせたかったのかもしれません。
「ビール瓶やコーラ瓶を持って行くと酒屋からお金がもらる」その対価をお小遣いとしてもらっていたのです。
あるとき、いつも通り「瓶ビールケース」を持って酒屋に行き、空き瓶ケースが置かれている場所に積み上げたところ、店主から怒られてしまいました。
「積み上げたら危ないだろ!」と。
そこは傾斜地でした。確かに、ちょっとした衝撃を受けると倒れる可能性があります。
しかし、裏の倉庫に運ぶのも面倒です。
空瓶ケースとはいえ5分ほど歩いて持ってきたので、手のひらが痛くて仕方ありません。
「こんなことが再三あっては嫌だな…」と思い、店主に提案しました。
「ここ(傾斜部分)に台を作っても良いですか?」と。
快諾してくれたので、早速材木屋に行って端材をもらい、空き地からレンガを拾ってきました。
簡易的ではありますが、レンガと木材がずれないように針金で結び、ケースが垂直に積める台を作ってあげたのです。
すると店主は喜び、当時の私にとって大金だった500円を渡してくれました。
当時、ビール瓶は1本5円。コーラ瓶はたしか1本20円で換金してくれていました。
「創意工夫は儲かる!」と感じたのを今でもよく憶えています。
次は、高校時代にアルバイトをしていた時のことです。
取得したばかりの原付免許を活かして弁当配達をしていたのですが、配達がないときの「チラシのポスティング」が嫌で嫌で仕方ありませんでした。
そこで、配達エリアにある火葬場にお願いして、チラシ立てに「弁当のチラシ」を置かせてもらったのです。仕出し弁当だったので、法事需要があると睨んだからです。
すると数日後、案の定30件もの法事用弁当の注文が入りました。
どうやら「この間来た子のチラシを見た」と電話で言ってくださったようで、店長は驚き、みんなの前で称賛してくれました。
どうやって交渉したのかを他の社員やアルバイトに説明する役割まで任され、時給は500円から650円へとランクアップしました。
そして、同店はポスティングではなく、営業活動に力を入れるようになったのです。
会社の会食需要や、代々木にあるテレビ局からのロケ弁まで受注するようになりました。
子ども時代の話なので事例は幼稚かもしれませんが――。
誰かのメリットにつながる「創意工夫」は、必ず結果として自分に返ってきます。
人と同じやり方ではなく、一歩違う角度から挑戦することが差別化となり、競争を避ける最良の手段となるのです。
他人を蹴落としたり、無謀に誇張する必要もありません。
常識やアタリマエを疑い、「より良い状態を作り出すためには…」と考えること。
それこそが、差別化の第一歩となるのです。
御社は、製品の差別化のみならず、販売の差別化まで、創意工夫を凝らした取り組みをされていますか?
