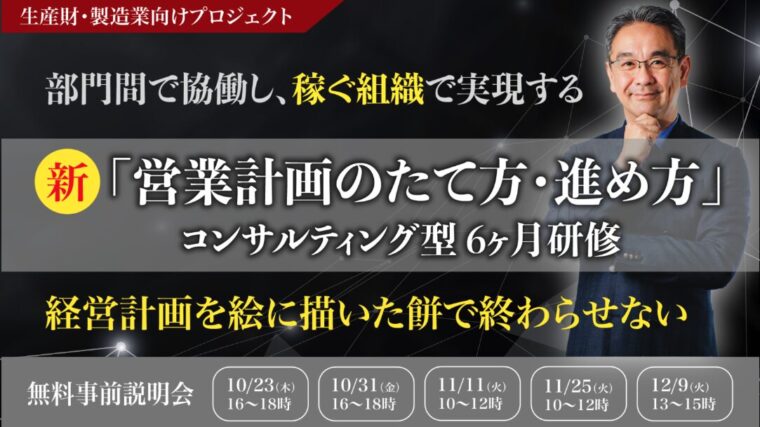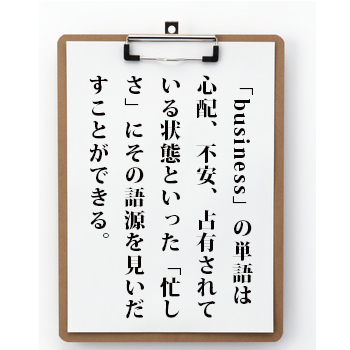
「別のコンサルタントから”社長業とは人格を隠し、役者に徹するべきだ”と言われました。藤冨さんはどう思いますか?」
これは先日、クライアント企業の社長さんと一献傾けながら、よもやま話をしていた際に出た話題です。
この言葉を聞いたとき、私は強い違和感を覚えました。
そして同時に、歴史観のない非常に雑な提言だと感じ、残念な気持ちになりました。
もちろん、捉え方や意見は人それぞれあるでしょう。
ですが、経営者がよほどの悪人でもない限り、自らを偽って“役者”を演じる必要など微塵もないはずです。
私の見解やその根拠をお伝えしたところ、件の社長も同じ感覚を抱いていたようで「相談して良かったです」とおっしゃってくださり、ホッと胸を撫で下ろしました。
今日のその「酒席でのよもやま話」を皆様とも共有したいと思います。
そもそも歴史的な文脈から紐解くと、私たち日本人のDNAには、仕事とは「神に仕えること」という思想が深く根付いているのではないでしょうか。
これは、先週のコラムでもお伝えした通り、神話を読み解くと、日本人にとっての「神」と「自然」の存在は非常に密接に関係しています。
太陽神である「天照大神」をはじめ、日本の神道における「八百万の神」の概念は、山、川、海、岩、風、火といったあらゆる自然現象や自然物に神が宿ると考えられています。
時に地震や雷、豪雨や台風などの猛威を振るう一方で、恵みと豊穣(ほうじょう)(太陽、雨、五穀)をもたらす源でもあります。
そうした自然と寄り添い、神と共生するように、人間同士の共同社会の営みとともに農耕社会が成り立ってきたわけです。
つまり、日本人のDNAに刻み込まれた「仕事観」とは、神々との共生、人々との共同社会を営むための存在であるはずなのです。
一方で、戦後アメリカ式の思考を刷り込まれた「ビジネス」という概念は、全く真逆の性格を持っています。
「business」という単語の起源を調べると、「心配、不安、占有されている状態」といった「忙しさ(busyness)」にその語源を見いだすことができます。
ここからは個人的な見解になりますが、この語源は、聖書の「創世記」からその背景を読み解くことができます。
聖書(創世記)では、人間が労働(仕事)を強いられるようになったきっかけは、次のように描かれています。
神から守られた「エデンの園」に住んでいたアダムとイブが、蛇に欺かれて禁断の果実を食べてしまいまった…。その結果、罰として、「人間」は恵まれた世界から追放されてしまった。
アダム(男性)に対しては、「汝は、額に汗を流してパンを得なさい」
イブ(女性)に対しては、「汝は、苦痛の中で子を産みなさい」
という神からの裁きがくだされるというストーリーです。
つまり、西洋においては「労働」はそもそも“罰”であり、罪の結果として課されたものというDNAが刻み込まれているのです。
「business」という概念は、神話から分析しても非常に納得のいく西欧の労働感です。
この労働観は、仕事という行為を、本来の安息(神との調和)を失った状態、すなわち「利潤追求」や「競争」によって現世の苦役から抜け出そうとする試練として描いています。
合理性・効率性・競争原理を重視し、時に人間性や倫理観よりも「成果」「数値」が優先される場面があるのは、この“原罪としての労働観”に起因しているとも言えるでしょう。
その流れを汲んだ「社長は人格を隠し、役者に徹するべきだ」という考え方には、「会社は戦場であり、経営者は演者として振る舞うべきだ」という西洋的なマネジメント思想が、無批判に輸入されているように感じます。
ですが、日本人のDNAにあらがうことなく従えば、社長とは“役を演じる存在”ではなく、「共同体のために全社一丸となって自然(神)と調和させるための指揮官」と捉える方がごくごく自然なのではないでしょうか。
ここでいう「自然」とは、「市場(顧客層)」や「取引先、サプライチェーン」をイメージしてお伝えしています。
抽象的な表現になってしまいますが、概して、この思考様式を企業文化として根付かせようと努力している経営者は、例外なく強靭な経営が実現できていると感じます。
給与、休暇、昇進など、表面的な動機づけに頼らず、真の意味で社員が働く意味や意義を感じているため、組織全体が強固な一体感を生み出していきます。
社員一人ひとりが「自らの役割を通じて共同体に貢献している」という誇りを持っているからでしょう。
日本アイ・オー・シーにおいても、顧客にベネフィットを提供することで「利益」を獲得していくことを「仕事の中心軸」に据えているのは、こうした信念にも近い思想を持っているためです。
ベネフィットの提供が先であり、利益は結果という主張です。
ドラッカーも、利益を「未来費用」と定義しています。
氏によれば、未来費用とは、企業が未来に挑戦し、存続していくために確保しなければならない「投資」だと捉えました。
さらに、ドラッカーは利益の使い道として、経営の目的である「顧客の創造」へ投資することが重要だと説きました。
この視点を深めると、企業の本質的な存在意義は、「顧客の創造」という活動を通じて、社会の成長と発展へ貢献することにあると理解できます。
つまり、ドラッカーの主張から見ても、企業は社会と共生・調和しながら、その役割を果たしていくべき存在だと言えるでしょう。
ところが、私たちが住む時代は今、断絶、分断など「つながりの喪失」が至るところで起きています。
国家間の対立、政治の対立、組織内のセクショナリズムなど―その背景には、西欧的な「ビジネス観」が横たわっているような気がしてなりません。
ドラッカーも高い評価を下していた「日本的経営」を本気で見直す時が来たようです。
御社は、日本人のDNAに寄り添った「仕事観」を大切にした「経営」を行いますか?
それとも、西欧から輸入してきた「ビジネス観」で経営をしていきますか?