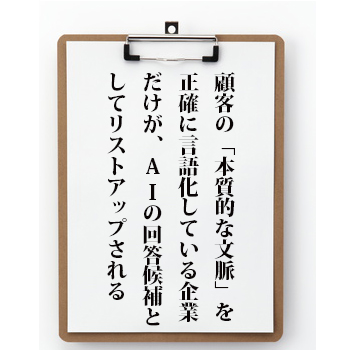
「ウチの会社は、営業の尻をたたくばかりで、商品力の向上をなおざりにしている感が否めません。 いつもコラムを読んでいて思いますが、我々だって、商品力があればもっと売れるはずだと思うのです」
まだお会いしたことのない読者さんから、憤りとも、切実な願いとも取れるメッセージをいただきました。
愚痴に聞こえる方もいるでしょうし、建設的な意見だと聞こえる方もいるでしょう。
実態を事細かに精査しないと、どちらとも言えませんが、ハッキリとしていることは、ただ1つです。
営業部門 対 技術・生産部門の対立構造が生まれ、それぞれの主義主張をぶつけ合うことが「仕事」となると、知らず知らずのうちに「会社の競争力」が消耗しまうリスクを増大させることです。
大袈裟に聞こえるかもしれませんが、これは間違いのない現実です。
営業マンは、顧客に正々堂々と価値を提供できると思えば、自社商品を強く推奨することができます。
相手の立場にたってパワフルに営業活動することが、自社の利益となって跳ね返ってくることを実感することは、ある種のエクスタシーを感じるものです。
しかしながら、営業マンが正々堂々と価値を提供できるという「自信」を失っている場合は、どうなるでしょうか。
人によっては、「自社の利益になるためなら…」と、自社の商品力の弱さや欠陥を知りながらも、半ば強引に売り込むという、最も辛く、そして長期的に見て最も会社を蝕む行動に出ます。
また、人によっては、真面目に働いているふりをしながら、力を出し切らず、クビにならない程度の働きで誤魔化す者もいるでしょう。
一見すると前者は会社に利益をもたらしているので、「優秀な人物」だと見えるかも知れません。
しかしながら、長期的な視点でみれば、「顧客の信頼関係を構築できず、その場しのぎの自転車操業体質を生み出す主犯格」として烙印を押される可能性があります。
後者は、会社だけでなく、自分自身をも騙し続けなければならず、良心の呵責に苛まれることになります。会社に損失を与えるだけでなく、自身のキャリアにも悪影響を与えてしまいます。
商品力に自信を持てない状況に目を背けたまま、営業活動をすることは、百害あって一利もないのです。
「いやー短期的でも利益になるのだから、一利くらいはあるでしょう」という反論する方もいるでしょうが、もはやそうした思考は「過去の遺物」となりつつあります。
なぜかーー。
それは、AI時代には「顧客側も考える力」が奪われるために、小手先の営業力では、勝敗がつかなくなる時代が、もうすでに始まりつつあるためです。
従来のネット検索では、企業ごとのホームページが一覧で紹介され、比較検討が前提となっていました。
つまり、顧客は自分の要求と商品の仕様を照らし合わせながら「考える」必要があったのです。
「考える」要素が多くなると、必然的に”誰か”に相談したくなります。
この”誰か”が、営業マンであるケースが多かったわけです。
しかし、検索エンジン型のAIである「perplexity」を使いこなしていると、時代が変わりつつあることに気づかされます。
AIは、ソリューションを優先的に提示してくれます。
現状抱えている課題をそのままAIに相談すると、最適な「解決方法」を提示してくれます。
そして、その解決方法を提供する企業や製品・サービスを検索すると、初めて「これまでのネット検索」のようなプレイヤー(企業や商品)を表示してくれるのです。
この現実を目の当たりにすると、いま私たちが取り組まなければいけない「課題」が明確になってきます。
「顧客は何に悩み、どのような課題を抱えているのか」
このファクトを正しく掌握することです。
これを掌握できない企業は、「AIの検索結果」にすら登場しない可能性が「大」だからです。
日本アイ・オー・シーでは、常日頃「お客様は製品を買っていない。ベネフィットを購入している」と呪文の様に繰り返し唱えています。
これを意味するところは、我々の製品は、どのように顧客の満足を満たしているのか…
この背景や理由などの文脈をどれだけリアルに掌握しているかー
ここを、言語化できている企業と、できていない企業とでは、AI時代の勝敗は“決定的”に違ってくるのです。
なぜなら、AIは「文脈」で意思決定を行うからです。
AIは、データベースではありません。
「文脈」を理解し、「文脈」から妥当解を生成しているのです。
つまり、顧客の“本質的な文脈”を正確に言語化している企業だけが、AIの回答候補としてリストアップされ、比較検討のスタートラインに立てるわけです。
これが示唆していることは、価値を伝える「営業部門」と価値を創造する「技術・生産部門」の連携が噛み合っていないと、顧客文脈が社内で一本化されず、発信する情報が“バラバラ”になってしまうということです。
営業は「顧客の痛点と欲求」を、技術・生産は「解決するための手段」を、それぞれ別々に語っていては機能不全を起こしてしまいます。
売上を規定するのは、「営業力」なのか「製品力」なのか、という二項対立の議論をしている時点で、AI時代の生存競争からドロップアウトされてしまう時代が、すでに到来していることに気づく必要があります。
価値を伝える営業。
価値を創造する技術・生産部門。
この双方が手を取り合って、初めて「マーケティング」という概念が、企業に根付いてくるのです。
ここから先の企業間競争は、「より深く顧客を理解している組織」vs「理解していない組織」というシンプルな構図になっていくことは間違いありません。
もはや、営業力か製品力かという論争をしている余地はありません。
今、求められるのは「顧客文脈を統合する力」です。
御社は、自社製品が顧客に利用されている「文脈」を正しく認識し、組織に行き届かせる「仕組み・体制」は存在していますか?
