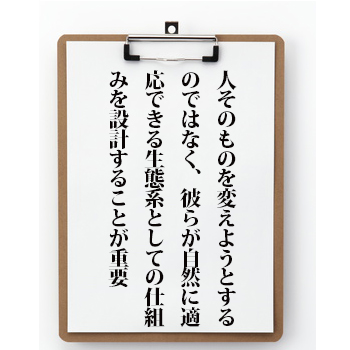
『若手営業マンと中堅・ベテラン営業マンの断絶を埋めるには、ゲーム感覚を取り入れることが必要かもしれませんね。』
先週、クライアント企業の社長さんが、現代的な社会課題を解決するヒントとして語っていた一言です。
個人的には、小学4年生の時に祖母に買ってもらったゲームウォッチやインベーダーゲームしか触れたことがなかったので、最初はピンと来なかったのですが…。
社長が「今の若者は、チュートリアルが無いと次に何をやっても良いのか分からないのかもしれない…」と続けた時、そこかも! と急にアンテナが立ったのです。
社会というのは、一つの生態系であって、一部が変わると全体も変化するのです。
例えば、1970年前後に生まれた若者が社会に進出し始めた1990年代、マスコミは彼らを「新人類」と名付け、まるで突然変異のように“異質な存在”として扱いました。
1969年生まれの私も、その渦中にいました。
当時感じていたのは、「自分たちは別に変わったことをしているつもりはない」という素朴な感覚でした。
しかし、戦争を体験してきた私たちの親世代からすると、高度経済成長を背景に、既存の価値観にこだわらない自由人的な価値観を体現し始めた私たち世代は、どこか頼りなく、危うく映っていたのだと思います。
価値観の前提が違えば、同じ行動でも「理解できないもの」に見えてしまう。
その構造が、時代の節目ごとに“世代間ギャップ”として現れてきたわけです。
そして今は、デジタルネイティブ世代が社会の主役に躍り出ようとしている時代。
私たちが“新人類”と言われた頃よりも、もっと急激な変化が起きています。
彼らは情報にアクセスするスピードも、学習の方法も、意思決定のプロセスも、根本から異なっています。
しかしその違いを「最近の若者は…」と片づけてしまうと、コミュニケーションは途端に断絶してしまう。
だからこそ、社長の言葉にあった「チュートリアルが無いと次に何をやれば良いのか分からない」という感覚は、決して批判ではなく、むしろ“新しい学習構造”を理解するための重要なヒントだと感じたのです。
ゲームの世界で「チュートリアル」と呼ばれている仕組みをYouTubeで調べてみると…
・最初にやるべきこと
・次に目指すべき地点
・到達すると手に入る報酬
・上達の兆しが可視化される仕組み
これらが明確に設計されていました。
もし営業組織にも、この“チュートリアル的設計”があれば、若手は迷走せず、ベテランは指導に余計なストレスを感じずに済むはずです。
そもそも若手営業マンを、過去の価値観や教育方法に合わせて育成しようとしても、うまくいきません。
彼らが変わったのではなく、彼らを取り巻く「環境」そのものが大きく変わったからです。
社会は一つの生態系であり、一部の人が変わったように見えても、むしろ環境の変化と人との相互作用の中で、全体が変化しているのです。
したがって、人そのものを変えようとするのではなく、彼らが自然に適応できる“生態系としての仕組み”を設計することが重要ではないでしょうか。
営業組織に「チュートリアル的設計」を組み込むことができれば、若手を迷走から救うだけでなく、世代を超えて“人が前に進む力”を引き出す普遍的な基盤になります。
なぜなら、中堅・ベテランにとっても、これまで暗黙知として語られてきた営業スキルが可視化され、振り返りや改善が容易になるからです。
つまり、“ゲーム感覚”は世代間の断絶を埋め、組織全体の成長速度を底上げする強力な橋渡し役になり得るのです。
では、この「チュートリアル的設計」をどのように現場へ落とし込むか。
その鍵を握るのが AIの活用 です。
具体的なイメージとしては、企業固有の情報資産をAIに“文脈ごと学習させる”仕組みを構築するアプローチです。
顧客企業の財務情報、CSRレポート、組織図、過去の提案書、納品仕様書…。
さらに、自社が持つ製品仕様、素材情報、技術的ベネフィット…。
これらをすべてAIに統合的に読み込ませておくと、AIは各種データの相関を理解し、「次にどのような提案をすべきか」を導き出す“ナビゲーション”を提供してくれます。
この要素技術は、すでにChatGPTを軽微にカスタマイズすることで動作することを確認できています。
このカスタマイズ精度をさらに洗練させることで、「最初にやるべきリサーチ」「確認すべき担当部署やキーマン」「提案の方向性」「具体的な提案書作成」「その提案が成約した場合に得られる売上・利益のシミュレーション」といった“営業チュートリアル”を自動的に提示させることができるはずです。
この構想を仕組み化できれば、単なるFAQの延長ではなく、取引先ごとの文脈(コンテキスト)に基づいた「営業戦略のインタラクティブガイド」になります。
もちろん既存取引先のクロスセル分野だけでなく、SFA(営業支援システム)と連携させることができれば、新規開発にも活用できます。
これが実現できれば、中堅やベテラン営業マンは、細かな指導から解放され、マネージャーは一人ひとりの進捗や課題をAIと共有しながら、本来時間を割くべき“高度な意思決定”に集中できるようになります。
そして何より重要なのは、AIが示すチュートリアルによって、営業プロセスそのものが構造化され、暗黙知が組織資産に変わることです。
経験者の頭の中だけにあったノウハウや判断基準が、AIのナビゲーションという形で“いつでも取り出せる知”に変換される。
この仕組みが整えば、組織の学習速度は飛躍的に向上し、世代を問わず「前に進むためのガイド」が等しく行き渡るようになるのでしょう。
設計には、企業単位での営業プロセスや蓄積すべき顧客情報などの精査が必要であり、利用方法についても「どこまでAIにやらせるか」といった研究も欠かせませんが、未来は確実に明るくなってきました。
2026年は、日本アイ・オー・シーでも「営業チュートリアル化」を研究・実証実験していきたいと考えています。
御社においても、新しい時代に適合した“若手営業育成の仕組み化”に取り組むタイミングが来ているのではないでしょうか。
