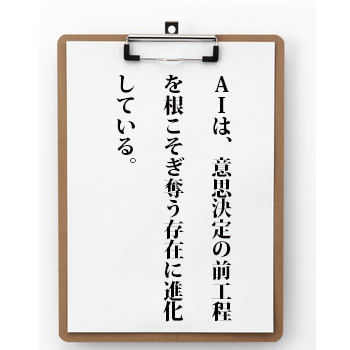
「AIが浸透すると、顧客の購買行動がどう変わるのか――もう少し詳しく解説してもらえませんか。」
先週のコラムにご意見を寄せてくださった読者の方から、続けて届いたご質問です。
ご質問をいただいた方は、部品製造業にお勤めの方のようなので、本稿では「生産財」を提供する企業に焦点を当てて、お答えしていきたいと思います。
さて、AIの社会浸透が進む中で、顧客の購買プロセスは何が、どう変わるのか。
インターネット普及の歩みを下敷きに、確実に起こり得る変化を段階的にお示ししたいと思います。
まず始めに、インターネットが誕生する「前後」について簡単に振り返ってみましょう。
インターネットが購買行動に影響を与えた本質的な役割は「情報の開放性」と「時間・コストの圧縮」です。
ネット普及前は、優れた製品や技術を企画開発できても、商社へのアクセス力や資本力がなければ「市場の認知度」を高めることはできませんでした。
しかし、ネットが普及した今では、自社が提供するソリューション力を認知してもらえる環境は、一夜にして作り込むことができるようになっています。
その結果、顧客は自社の課題を解決するためにネットを検索し、メーカーや技術提供企業に瞬時にアクセスできるようになったのは、皆様も体感している通りです。
これにより1990年初頭から、いわゆる「中抜き問題」(卸売業不要論)がテレビや新聞で騒がれました。
実際、自動車卸売業では1991年に2万2千件あった事業所が、2021年には1万8千件まで減少。売上高は3.3兆円から2.2兆円と3割以上減少するなど、インターネットは商慣行に大きな影響力を与えてきました。
現場を見聞きすると、勝ち残った卸売企業でも、仕事の内容が大きく変化しています。
「昔とは違い、今はメーカーから“型番指定”で見積依頼が来ます。私たちは、メーカーの指示に従って情報を収集する手足のような仕事が増えてきています」と、嘆きにも聞こえる声があちこちから上がっています。
メーカーが画期的な技術を開発しても、商社や卸売業者は「頼まれごと」に追われており、「新たな提案をする時間」がないというのが、現状の通説です。
インターネットは、買い手の「選択肢」を広げ、「比較検討」を容易にし、「交渉」の自由度を高めていきました。
つまり、インターネットの変化の本質は「情報の開放性」と「時間・コストの圧縮」によって、顧客の購買行動に根本的な変化をもたらしたのです。
では、AIやAIエージェントの社会浸透がもたらす本質的な影響とは何でしょうか?
それは、これまでの「知る・比較する・交渉する」から、次の段階である「予測し・代行し・最適化する」へと、情報効率を飛躍的に高める社会の到来を意味しています。
言い換えれば、「意思決定と行動の代行および最適化」がシステムによって担われる世界が、まさに目の前に来ているのです。
「これから」のことではありません。
私たちはAmazonの「あなたへのおすすめ」や、YouTubeやNetflixの「次に見るべき作品」、さらには追跡型広告(リターゲティング広告)など、すでに体験している世界なのです。
これによって、人々(企業)の購買行動はどう変わるかー。
前回、際どい言葉でお示しした「考えない消費者」が一般化してくるのです。
例えば、「生産ラインで不具合が起きる」という問題があると、人間が「どうすれば良いか?」を考えていました。
そして、「こんな解決策を持っている企業はないか?」と検索エンジンを駆使して調べ上げ、優れた技術や製品にアクセスしていたのが、ネット時代の購買行動でした。
「課題や問題」の発生した原因は何か。
どうすれば、「問題」をよりよく解決できるか…と「人間」が考えていたのです。
したがって、解決策…いわゆるソリューション提案を的確に情報発信している企業に、注目が集まり、受注が集中していたのが、インターネット時代だったわけです。
ところが、AIはこれらの「考えるプロセス」を一気に「中抜き」してくれます。
「現状」と「悩み」をAIに入力すると、問題点や問題の背景を示した上で、解決策まで一気に提示してくれます。
煩わしいネットサーフィンや、どこに何が書いてあるかわかりにくいホームページからもAIは私たちを解放してくれます。
さらに言うと、AIエージェントを使えば、情報収集した結果を自動的にエクセル(スプレッドシート)に転記し、ワード(ドキュメント)で比較検討レポートも瞬時に作成してくれるまで、プロダクトが成長しています。
AIは、単に「情報を出す」存在ではなく、「意思決定の前工程を根こそぎ奪う」存在に進化しているのです。
米国のテック企業が先月から大規模なリストラを発表していることは、『業務の自動化』が確実視されていることを強く示唆しています。
(Amazon約1万4千人、Microsoft約9千人、MetaはAI部門を中心に600人リストラ発表)
こうした AI が浸透していく「環境変化」に置かれた私たちは、AI に順応した “購買行動” を取らざるを得なくなっていきます。
なぜなら、AIを活用して仕事を進めることが日常になれば、自然とAIがあなたの仕事を推測し、あなたが求めていることを”先回りして提示してくれる”ようになるからです。
そうなると、これまで企業からの情報発信は「ソリューションの提案」だけで良かったものから、顧客の現状や悩み、課題、問題点まで丁寧に情報を発信する必要が出てくるわけです。
これからの買い手は、AIに現状や悩み、課題、問題を入力し、解を求めてきます。
となると、売り手である企業は、「買い手の現状、課題、問題点」と「売り手のソリューション」をセットにした情報をLLM(大規模言語モデル)に学習させた方が、露出が高まるわけです。
これは言い換えれば、「顧客の現状や課題、問題点をどこまで高い解像度で把握しているか」という、技術部門・営業部門双方に向けた問いを突きつけています。
生産財メーカーの営業担当者と会話をしていると、「自社製品がどのような背景や理由、どのような利用シーンで使われているのか」というコンテキスト(文脈)を十分に把握していないケースが散見されます。
一方、この構造に気づいている企業は、社内で蓄積すべき情報の再定義に着手し、次の時代に向けた布石を打ち始めています。
なぜか。
今後は “人間が情報を探索する時代” ではなく、“AIが探索し、人間が最終意思決定する時代” に移行すると予測しているからです。
つまり、将来の勝ち組企業は、どの情報をAIに学習させるか、という視点で「価値の伝え方」を設計し直すステージに入っているのです。
御社は、自社製品や技術が導入された「背景」「理由」「利用シーン」といったコンテキスト(文脈)を、共通言語として社内に蓄積し、情報発信の材料として活用する準備を進めていますでしょうか?
AI時代の勝者は、「顧客コンテキスト」を最も深く握った企業です。
