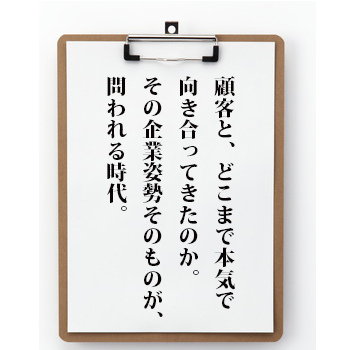
『ウチには製品開発担当がいるので、この部門で企画の機能も担わせようかと考えていますが……新たな担当をつけた方が良いのでしょうか?』
先週のコラムを読んだ読者さんから、こんな質問をいただきました。
とても現実的で、むしろ「よく考えている」からこそ出てくる問いだと思います。
というのも、実際の現場には、顧客の世界に深く入り込み、課題を理解しようとする姿勢を持った製品開発部門が、確かに存在するからです。
「開発は作るだけ」「顧客理解は企画の仕事」そんな単純な切り分けでは語れないケースが、増えてきています。
そこで今回のコラムでは、商品企画と製品開発を「役割」で分けるのではなく、思考の“集中領域”の違いとして整理してみたいと思います。
まず、商品企画の役割は、極めて深淵ではあるものの「構造」としては、とてもシンプルです。
顧客の世界に、どっぷり浸かり、どんな環境に置かれているのか、どんな不満足を「仕方ない」と受け入れているのか、なぜ、その問題は放置され続けてきたのか…ここに、徹底的に向き合います。
しかしながら、このヒアリングの段階で「モノレベル」で解決策を考えてしまうと、顧客の真のお困りごとや痛点を掘り下げることができなくなってしまいます。
子育てを経験したことがある方なら、ピンとくるかも知れません。
子供が誤って高価なワイングラスを割ってしまったとしましょう。
事実だけ捉えて、「コラッ!いつも言っているじゃない!」と怒ってしまっては、真実を捉えることはできません。
そもそも、感情的になるのは論外です。
また、「そんな場合は、こうすれば良い!』と解決策を提示してしまうことも、重要なファクトを見逃すことになります。
真の原因を掴んでいないので、応用が効かず、「また同じような失敗」を形を変えて繰り返すことになります。
ここで目を向けるべきは、表面的な「グラスが割れた」という事象ではなく、その背後にある構造的な原因や子供の心理状態です。
「なぜ子供の手が届く場所に、そのグラスがあったのか?」
「子供の今の運動能力にとって、そのグラスは重すぎたり、滑りやすかったりしなかったか?」
「子供は何かに焦っていたのか、あるいは好奇心から「触ってみたかった」だけなのか?
ファクトを掴むことで、本質的かつ根本的な解決アプローチを導き出せるかも知れないのです。
ビジネスでも同様です。
このファクトを浮き彫りにするには、まずは先入観を捨てて、顧客の世界に没入する必要があるのです。
企画の役割は、モノレベルで解決策を考えることなく、また解決アイデアの有無を考えることなく、まずは『顧客の現状とあるべき姿』を探求していくことが、大切なのです。
一方、製品開発は、まったく違う難しさを背負っています。
製品開発は、顧客の課題を理解したうえで、「品質は担保できるか」「コストは見合うか」「技術的な課題は解決できるか」など、作り手側の制約とも同時に向き合わなければなりません。
つまり、製品開発は、顧客側と作り手側、二つの世界を往復する仕事なのです。
問題は、この二つの思考が、同時に走り出してしまうときに起こります。
顧客分析の途中で解決策が先に浮かんでしまうと、 作り手の思考は一気に「実現モード」へと切り替わります。
その瞬間、関心は、「顧客が何に困っているのか」から、 「どうやって作るか」へと移り、 顧客そのものが、視界から外れてしまうのです。
上述した「子供のワイングラス事件」と一緒です。
また、到底解決できそうにないことや、過去に失敗した経験があると、実現性のブレーキが、無意識にかかり始めてしまいます。
すると、どうなるか。
問いは、自然とこう変質していきます。
本当は何に困っているのかではなく、今の技術で対応できる困りごとは何か…と。
結果として、顧客の課題は「表面的な改善要望」に縮んでいきます。
ちょっとした改善……もちろん、それも価値提供です。
しかし、その延長線上にあるのは、どんぐりの背比べに陥りやすい改良競争であって、自社の未来を築く「顧客の創造」ではありません。
だからこそ、商品企画のフェーズでは、あえて実現性を考えない。
極端に言えば、「それ、本当に困ってる?」を、しつこく問い続ける役割が必要なのです。
その問いを十分に掘り切ったあとで、初めて製品開発が登場する。
「では、それをどう解くか」「今の技術と制約の中で、どこまでできるか」
この順番を守ることで、顧客理解は一段と深くなり、開発の打ち手も、鋭さを増していきます。
顧客が自らの痛点やニーズに気づいていないときこそ、「売れる企画」のチャンスが眠っているものです。
今後、このアプローチは、ますます不可欠なものになっていきます。
なぜなら私たちは今、GoogleやYahoo!の検索窓に「解決策の名前」を打ち込む時代から、ChatGPTやGeminiに「いま抱えている困りごと」そのものを入力する時代へと、移行しつつあるからです。
つまり、顧客の痛点を深く掘り下げ、「何を解くべきか」を企画できる組織こそが、生成AIを真の味方につけることができるのです。
SEOからLLMOの時代への移行は、単なるITスキルやツール活用の問題ではありません。
顧客と、どこまで本気で向き合ってきたのか。
その企業姿勢そのものが、問われているのです。
御社は、顧客の痛点を掘り下げる組織文化を醸成しようとしていますか?
【用語解説】
SEO:Googleなどの検索結果でWebサイトを上位に表示させ、自然検索からのアクセスを増やす施策
LLMO:ChatGPTやGeminiなどの生成AIが回答を生成する際、自社のWebコンテンツが情報源として引用・参照されやすくする施策。
今後、生成AIの広告運用が開始されると、コンテンツと広告の親和性が重視されるので、より一層重要なテーマとなります。
